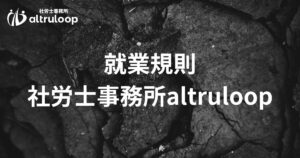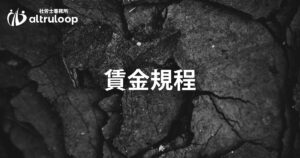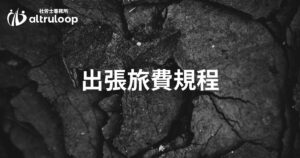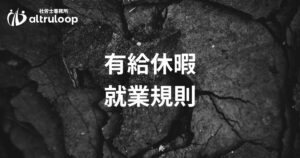昨今、「パワハラ防止法」と呼ばれる法改正により、職場のハラスメント対策が全ての企業で義務化されました。そのため就業規則にもハラスメントに関する規程を盛り込む重要性が一段と高まっています。しかし、「何をどう記載すれば良いのか分からない」「自社の就業規則が法律に対応できているか不安」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では 就業規則のハラスメント規程の必要性や具体的な記載例、作成のポイントについて、社会保険労務士がわかりやすく解説します。ハラスメント規定づくりのコツと専門家へ相談するメリットもご紹介しますので、自社の職場環境整備にぜひお役立てください。
ハラスメント規程はなぜ必要?
ハラスメント規程とは、職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の行為を禁止し、問題発生時の対処方法などを定める就業規則上のルールのことです。かつてハラスメント対策は努力義務にとどまっていましたが、2022年4月からは中小企業も含めて事業主にハラスメント防止措置が義務化されています。これは法律(改正労働施策総合推進法)の施行により、中小企業においてもハラスメント防止のために必要な措置を講じなければならなくなったためです。
具体的に事業主が講ずべき措置としては、ハラスメント行為をしてはならない旨の方針を定め周知することや、行為者に厳正に対処する方針・内容を就業規則等の文書に記載し労働者に周知することなどが挙げられています。言い換えれば、「うちの会社ではあらゆるハラスメントを許さない」という方針と具体的ルールを社内規程として明文化し、従業員に知らせておくことが法律上求められているのです。就業規則にハラスメントの記載を設けておけば、社員全員に対して会社の方針を示せるだけでなく、万一問題が起きた際にもルールに基づいた適切な対応・処分が可能になります。
もしハラスメント規程が未整備だとどうなるでしょうか? 社員がハラスメント被害を受けても相談窓口や処分のルールが曖昧だと、適切な対処が遅れ被害が拡大する恐れがあります。また加害者への懲戒処分を巡って「就業規則に規程がない」と争われるリスクもあります。ハラスメント対策義務に違反しても直接の罰則はありませんが、行政から是正指導や勧告を受ける可能性があり、企業の信用失墜にもつながりかねません。従業員を守り職場の秩序を保つため、就業規則に明確なハラスメント規程を設けておくことが非常に大切なのです。
就業規則に盛り込むべきハラスメント規程の内容
それでは、具体的に就業規則にはどのようなハラスメント規程を盛り込めばよいのでしょうか。一般的に、以下のようなポイントを規程します。
対象となるハラスメントの種類と定義
職場で起こり得るハラスメントには様々な種類がありますが、特に法律上対策が義務付けられているものは主に次の3種類です(セクハラ、マタハラ等も含め「妊娠・出産等に関するハラスメント」として扱われます)。
パワーハラスメント(パワハラ)
職場の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超える言動で他の労働者に身体的・精神的苦痛を与えたり、就業環境を害する行為。暴力・暴言だけでなく、過大な業務を押し付ける、逆に仕事を与えないといった行為も該当します。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)
職場における性的な言動により、労働者が不利益を被ったり就業環境が悪化する行為。本人が望まない性的冗談や不必要な身体接触などが典型例です。
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタハラ等)
妊娠・出産、育児休業や介護休業の取得等を理由に、上司や同僚が嫌がらせを行い就業環境を害する行為。妊娠中の女性社員に対する心ない発言や、育休復帰者への嫌がらせなどが該当します。
※近年はSOGIハラスメント(性的指向や性自認に関するハラスメント)も問題視されています。例えばLGBTの従業員に対する心ない言動や、本人の了承なく性的指向を暴露する行為などがそれに当たります。これらはセクハラやパワハラの一種として扱われるため、社内で起こり得るハラスメントの種類として認識し、防止策に含めることが望ましいでしょう。
ハラスメント行為の禁止と具体例
上記の定義を明記したら、「従業員は職場においてハラスメント行為を行ってはならない」旨を就業規則に記載します。その際、どのような言動がハラスメントに当たるのか具体例を挙げておくと効果的です。例えば「暴行・脅迫などの身体的攻撃」「侮辱や差別的発言などの精神的攻撃」「性的な冗談や不必要な接触」など、種類ごとに具体的な禁止事項を列挙します。また、上司や管理職が部下のハラスメント被害を知りながら放置する行為も禁止すべき重要事項です。会社としてハラスメントを見逃さず厳正に対処する姿勢を示すため、黙認の禁止も規程に入れておきましょう。
相談窓口の設置と対応体制
ハラスメント防止措置として、相談や苦情に適切に対応するための体制整備も義務となっています。就業規則や社内規程で相談窓口を定め、従業員へ周知することが必要です。誰が窓口担当者になるか(例:人事部長、外部相談窓口の連絡先など)を明記し、相談があった場合の対応手順も社内で決めておきます。就業規則の規程例では「各種ハラスメントに関する相談窓口は○○部とし、責任者は○○とする」等と定められています。併せてプライバシー保護義務や相談者・協力者への不利益取扱い禁止も忘れずに明文化しましょう。例えば「相談したことや調査に協力したことを理由に不利益な扱いをしてはならない」と記載し、安心して相談できる環境を約束します。
懲戒処分規程との連動
ハラスメント行為が発覚した際に適切なペナルティを科すため、就業規則の懲戒事由にハラスメント行為を含めておくことも重要です。例えば「従業員がハラスメント行為を行ったときは◯◯の懲戒処分を科す」といった具合に、処分の種類(戒告、減給、出勤停止、懲戒解雇など)を記載します。就業規則上に定めがあれば、加害者への厳正な対処が法的に裏付けられるため、被害者も安心でき社内の抑止力にもなります。特に中小企業では懲戒処分の手続きが整備されていないケースもありますので、ハラスメント規程と合わせて懲戒規程も見直しておくとよいでしょう。
以上がハラスメント規程の主な内容です。これらを網羅的に記載することで、ハラスメント防止に必要な社内ルールの骨子が整います。次に、実際のハラスメント規程の記載例を見てみましょう。
ハラスメント規程の記載例(サンプル条文)
就業規則や付属の「ハラスメント防止規程」における具体的な条文の一例をご紹介します。自社の規程を作成する際の参考にしてください。
(目的) 第○条 本規程は、就業規則に付属する別規程として、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防止するために従業員が遵守すべき事項を定める。
(定義) 第○○条 パワーハラスメントとは、地位や人間関係など職場における優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により他の労働者に精神的又は身体的な苦痛を与え、若しくは就業環境を害することをいう。ただし、業務上必要かつ適正な指導・業務指示はこれに該当しない。
(禁止行為) 第○○条 従業員は職場内において、いかなるハラスメント行為も行ってはならない。以下に掲げる行為は禁止事項の例とする。
- 暴行・脅迫などにより他の従業員に身体的な危害を加える行為
- 業務上必要のない侮辱的な発言や隔離・無視などにより他の従業員に精神的苦痛を与える行為
- 相手の意に反する性的な言動を執拗に行い、他の従業員に不快感を与える行為
- 妊娠・出産・育児休業等の制度利用者に対し嫌がらせ発言をする行為
- 部下や同僚がハラスメント被害を受けている事実を知りながら、これを放置・黙認する行為
(相談窓口) 第○○条 ハラスメントに関する相談窓口は○○部とし、その責任者を○○と定める。相談窓口の担当者は相談者のプライバシー保護に十分配慮しなければならない。相談や報告を行ったことを理由として、当該従業員に不利益な取扱いをしてはならない。
上記は一例ですが、厚生労働省や各労働局でも類似の規程例やモデル就業規則が公開されています。
自社で条文を作成する際にはこれらも参考に、業種や会社規模に応じた内容にカスタマイズすると良いでしょう。ただし、ネット上のひな形をそのまま写すだけでは自社の実態に合わない恐れがあります。例えば従業員数や部署体制によって相談窓口の設置方法も変わりますので、自社の実情に合わせて条文を調整することが重要です。
ハラスメント規程を作成・導入する手順とポイント
ハラスメント規程を就業規則に盛り込む手順を、段階的に確認しておきましょう。既存の就業規則がある場合も、新たに規程を追加・改定する形で対応します。
1,現状の把握と準備
自社で起こり得るハラスメントのリスクや、現行就業規則の内容をまず確認します。パワハラ・セクハラ防止措置義務の内容(相談窓口の設置など)を把握し、どの部分を規程に反映すべきか洗い出しましょう。既にハラスメント方針を社内通知している場合も、改めて就業規則上に明文化する必要があります。
2,規程案の作成
前章で述べた項目(定義、禁止事項、相談窓口、懲戒など)について草案を作ります。既存の就業規則がある場合は、「服務規律」や「懲戒」の章にハラスメント禁止条項を追加し、詳細は別添の「ハラスメント防止規程」に定める方法が一般的です。一方、就業規則自体がない場合(社員10人未満で未作成の場合など)でも、トラブル防止のため社内規程として自主的に整備しておくことをおすすめします。
3,社員代表等との協議
就業規則の変更には労使間の合意形成が大切です。従業員の代表者(労働組合または社員代表)に規程案を示し、内容に問題がないか確認・意見聴取します。ハラスメント防止は従業員にとっても安心材料になる旨を説明し、協力を得ましょう。
4,労基署への届け出(必要に応じて)
常時10名以上の従業員がいる事業場では、就業規則の作成・変更時に所轄の労働基準監督署へ届け出る義務があります。ハラスメント防止規程を別規程として作成した場合も就業規則の一部として提出することを忘れないようにしましょう(書類の備え付け・届出が必要です)。逆に従業員10名未満で届け出義務がない場合でも、社内で規程を周知することは必須です。
5,従業員への周知
新たに策定・変更したハラスメント規程は、必ず全従業員に周知します。就業規則本体や別規程を社内掲示板やイントラネットに掲載したり、書面・データで配布してください。単に配布するだけでなく、朝礼や研修などで周知徹底を図ることも効果的です。また、難しい法的表現だけでなくイラストやQ&A形式のガイドラインを作成し従業員に配布すると、内容が伝わりやすく予防効果が高まります。
6,定期的な見直しと教育
ハラスメントに関する法律や社会状況は変化します。就業規則の内容も定期的に見直し、最新の法令に適合させましょう。従業員研修やアンケートを通じて職場の実態を把握し、必要に応じて規程を修正・補強することも大切です。常に職場全体で「ハラスメントを許さない」意識を共有するよう、継続的な教育・啓発にも努めましょう。
以上のステップを踏むことで、自社の就業規則に適切なハラスメント規程を導入することができます。しかし実際には法律の専門知識を要する作業も多く、「自社だけで作成するのは不安」という場合もあるでしょう。そのようなときは無理をせず、社会保険労務士(社労士)など労務の専門家に相談することをおすすめします。次の章では、専門家に依頼するメリットについて説明します。
社労士に相談するメリット
就業規則のハラスメント規程を専門家に依頼することで、得られるメリットは多岐にわたります。ここでは社労士に相談する主な利点をまとめます。
最新の法令に完全準拠した就業規則を作成できる
社労士は労働法規のプロフェッショナルです。2020年施行のパワハラ防止法や関連指針など最新の法改正内容もしっかり踏まえ、漏れのない規程を作成してもらえます。自社だけでは見落としがちなポイントも専門家なら安心です。
自社の実態に合わせたオーダーメイドの規程
ひな形を加工するだけではなく、社労士は各社の事情に応じたカスタマイズを行ってくれます。業種や従業員規模、過去のトラブル事例などをヒアリングした上で、「自社に本当に必要な内容」を盛り込んだ就業規則を整備できます。また中小企業特有の課題にも精通している社労士であれば、きめ細かな対応が可能です。
従業員トラブルのリスク軽減
適切なハラスメント規程を設け周知することで、将来的なトラブル発生リスクを下げる効果が期待できます。しかし万一ハラスメント問題が起きてしまった場合でも、就業規則がしっかりしていれば会社としてブレない対応ができます。社労士は就業規則整備のみならず、問題発生時の対処法についてもアドバイスしてくれるため、アフターフォローも万全です。
手間の削減と本業への専念
法令調査や書類作成に時間を取られると、本来の業務に支障が出てしまいます。専門家に依頼すれば煩雑な手続きを任せられるので、経営者や人事担当者は本業に集中できます。特に全国に支店がある場合でも、社労士事務所によってはオンラインで全国対応してくれるところもありますので、遠方からでもスムーズに相談・依頼が可能です。
まとめ
本記事ではハラスメント規程について解説させていただきました。
社労士事務所altruloop(アルトゥルループ)では、全国対応・初回相談無料でご相談を承っております。人事労務に関するお悩みはお問い合わせよりお気軽にご相談ください。