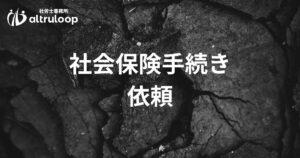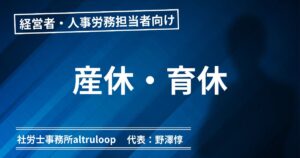社会保険の手続きの中でも、特に「月額変更届」は中小企業の経営者や人事担当者の皆様にとって、対応が必要となる場面がありながらも、その複雑さから戸惑うことの多い手続きの一つではないでしょうか。本業でお忙しい中、専門知識が求められる書類作成や計算、法改正への対応、そして万が一の提出漏れや計算ミスによるペナルティは避けたいものです。
この記事では、月額変更届(正式名称:健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)について、その基本から具体的な手続き方法、注意点に至るまで、社会保険労務士が分かりやすく徹底解説します。月額変更届が「いつ、どんなときに必要なのか」「対象者は誰か」「どのように計算し、書類を作成・提出するのか」といった疑問にお答えし、算定基礎届との違いや、手続きを怠った場合のリスクについても詳しくご説明します。
この記事をお読みいただくことで、月額変更届に関する不安を解消し、正確かつスムーズな手続きを進めるための一助となれば幸いです。
月額変更届とは? どんなときに必要?
月額変更届とは、従業員の給与(報酬)に大幅な変動があった場合に、健康保険や厚生年金保険の保険料計算の基礎となる「標準報酬月額」を見直すために提出する書類です 。この手続きは「随時改定」とも呼ばれ、年に一度行われる「定時決定(算定基礎届の提出による改定)」とは異なり、給与変動に応じてその都度行われます 。
この手続きの目的は、従業員が実際に受け取る報酬額と標準報酬月額が大きくかけ離れることを防ぎ、社会保険料や将来受け取る年金額が実態に即した適正なものとなるようにするためです 。もし、給与が大幅に変わったにもかかわらず標準報酬月額が以前のままですと、保険料の負担が不公平になったり、将来の年金給付額に影響が出たりする可能性があるため、この月額変更届による随時改定が重要な役割を果たします。
標準報酬月額の改定とは
月額変更届を理解する上で欠かせないのが「標準報酬月額」という考え方です。標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料、そして将来の年金給付額を計算する際に用いられる基準額のことです。毎月の給与額そのものではなく、給与額を一定の範囲(等級)に区分し、その等級ごとに定められた金額を指します 。健康保険では都道府県ごとに、厚生年金保険では全国共通の等級表が定められています。
通常、この標準報酬月額は年に一度、4月・5月・6月の給与を基に決定され(これを「定時決定」といい、「算定基礎届」を提出します)、その年の9月から翌年8月まで適用されます。しかし、年の途中で昇給や降給などにより給与が大幅に変動した場合、この定時決定を待っていては実態と合わなくなってしまいます。そこで、定時決定を待たずに、実態に合わせて標準報酬月額を改定するのが「随時改定」であり、その際に提出するのが月額変更届なのです 。
月額変更届の「対象となる変更」の種類
月額変更届の提出が必要となるのは、原則として「固定的賃金」に変動があった場合です 。固定的賃金とは、毎月決まって支払われる賃金のことで、具体的には以下のようなものが該当します。
- 昇給、降給
- 基本給の変更
- 住宅手当、家族手当、役職手当、通勤手当(金額が固定されている場合)などの固定的な手当の支給額変更、新設、廃止
- 給与体系の変更(例:日給制から月給制への変更など)
- 歩合給や出来高給の単価や支給率の変更(固定的な計算方法に基づく場合)
一方で、残業手当やインセンティブのように、月々の実績によって変動する「非固定的賃金」のみの変動では、原則として月額変更届の対象とはなりません 。ただし、固定的賃金の変動があった上で、非固定的賃金を含めた3ヶ月間の平均報酬月額が大きく変わる場合には、月額変更届が必要となる点に注意が必要です。この点は後ほど詳しく解説します。
月額変更届の対象者は? 間違いやすいケース
月額変更届の対象となるのは、健康保険および厚生年金保険に加入している従業員(70歳以上の被用者を含む場合があります)のうち、以下の3つの条件をすべて満たした場合です 。これらの条件は非常に重要であり、一つでも満たさない場合は原則として月額変更届の提出は不要となります。
- 固定的賃金に変動があったこと
前述の通り、基本給や固定的な手当の額、給与体系などに変更があった場合です。 - 変動後の継続した3ヶ月間に支払われた報酬の平均月額から算出した標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと
固定的賃金の変動後、実際に支払われた3ヶ月間の報酬(固定的賃金だけでなく、残業代などの非固定的賃金も含む)の平均額を算出し、それを標準報酬月額等級表に当てはめた結果、現在の標準報酬月額の等級と比べて2等級以上の差(昇給・降給どちらの場合も)が生じることが必要です。 - 変動後の継続した3ヶ月間の各月の支払基礎日数が17日以上であること
支払基礎日数とは、給与計算の対象となった日数のことです。この支払基礎日数が、固定的賃金が変動した後の3ヶ月間、いずれの月も17日以上である必要があります。ただし、特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合は、11日以上となる場合があります 。
この「3つの条件をすべて満たす」という点が、月額変更届の要否を判断する上での最大のポイントです。例えば、大幅な昇給(固定的賃金の変動)があっても、その後の3ヶ月間のうち1ヶ月でも支払基礎日数が17日未満であれば、原則として月額変更の対象とはなりません。また、固定的賃金の変動自体は1等級程度の差であっても、その後の残業時間の増加などにより、非固定的賃金を含めた3ヶ月平均の報酬が結果として2等級以上の差を生じさせた場合には、月額変更の対象となることがあります 。
月額変更届の「対象者」の条件をチェック
自社の従業員が月額変更届の対象となるかどうかを判断するために、以下のチェックポイントを確認しましょう。
固定的賃金に変動はありましたか?
- 基本給の昇給・降給
- 役職手当、住宅手当、家族手当、固定の通勤手当などの新設・増額・減額・廃止
- 給与体系の変更(例:時給制から月給制へ)
- 固定残業代の金額変更 など
固定的賃金変動後の3ヶ月間、各月の支払基礎日数は17日以上(または11日以上)ですか?
支払基礎日数の数え方
- 月給制・週給制の場合:暦日数(欠勤控除がある場合は、就業規則等で定められた所定労働日数から欠勤日数を控除した日数)
- 日給制・時給制の場合:出勤日数
短時間労働者の特例
特定適用事業所等に勤務する短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上など一定の条件を満たす方)の場合は、支払基礎日数が11日以上であれば要件を満たすことがあります 。
固定的賃金変動後の3ヶ月間の平均報酬月額から算出した新しい標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じますか?
この確認には、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額等級表が必要です(計算方法の章で詳述します)。
例外的な1等級差での改定
標準報酬月額の等級が上限または下限に該当する場合、1等級の変動でも随時改定の対象となることがあります 。これは、実質的に2等級以上の変動とみなされるためです。
これらの条件を一つずつ丁寧に確認することが、正確な手続きへの第一歩です。特に支払基礎日数のカウント方法は給与形態によって異なるため、注意が必要です。
月額変更届の「対象外」となるケースも確認
上記の3つの条件をすべて満たさない場合は、原則として月額変更届の提出は不要です。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 固定的賃金に変動がない場合:例えば、残業時間の増減だけで給与総額が大きく変わったとしても、基本給などの固定的賃金に変動がなければ対象外です 。
- 固定的賃金に変動はあったが、変動後の3ヶ月間の平均報酬月額による標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じなかった場合。
- 固定的賃金に変動はあったが、変動後の3ヶ月間の支払基礎日数が1ヶ月でも17日(または11日)未満だった場合。
- 固定的賃金は増加したが、残業代などの非固定的賃金が大幅に減少したため、結果として標準報酬月額の等級差が2等級未満となった場合(またはその逆のケース)。
- 賞与(ボーナス)が支給された場合:年3回以下の賞与は、月額変更届ではなく「被保険者賞与支払届」の対象となります 。ただし、年4回以上支給される賞与は、標準報酬月額の算定基礎に含まれる「報酬」とみなされるため、この限りではありません。
- 一時的な手当の支給:慶弔見舞金など、臨時に支払われる性質の手当で、固定的賃金に該当しないものは対象外です。
これらのケースを理解しておくことで、不要な手続きを避け、必要な手続きに集中することができます。特に、固定的賃金と非固定的賃金の変動が複雑に絡み合う場合は判断が難しくなるため、慎重な確認が求められます。
月額変更届は「いつ」提出? 提出時期と期限
月額変更届の提出時期について、多くの担当者様が気にされる点かと思います。結論から申し上げますと、月額変更届には「何月何日までに提出」といった厳密な日付の期限は法律上定められていません。しかし、「速やかに」提出することが求められています 。
「速やかに」とは、随時改定の3つの条件をすべて満たしたことが確認でき次第、遅滞なく手続きを行うという意味です。通常、固定的賃金の変動があった月から3ヶ月間の給与支払いと支払基礎日数が確定した時点で、随時改定の該否が判断できますので、その後できるだけ早く提出することが望ましいでしょう。
月額変更届の「提出時期」の基本ルール
月額変更届の提出時期の基本ルールは「随時改定の要件を満たしたら速やかに」です。なぜ速やかな提出が求められるかというと、提出が遅れると、改定後の新しい標準報酬月額の適用が遅れ、その結果、社会保険料の徴収額に過不足が生じたり、従業員の将来の年金給付額の計算に影響が出たりする可能性があるためです 。
月額変更届に記載する「改定年月」は、実際に新しい標準報酬月額が適用される月のことであり、これは固定的賃金の変動があった月から数えて4ヶ月目となります 。
例えば、
- 4月に昇給があり、4月分の給与から昇給額が反映された場合(当月払い):
- 算定対象月:4月、5月、6月
- 改定年月(新保険料適用開始):7月
- 4月に昇給があり、4月分の給与(昇給額反映)が5月に支払われた場合(翌月払い):
- 算定対象月:5月支払い分(4月分給与)、6月支払い分(5月分給与)、7月支払い分(6月分給与)
- 改定年月(新保険料適用開始):8月
このように、会社の給与支払いサイクル(当月払いか翌月払いか)によって、算定対象となる支払月と改定年月が変動する点に注意が必要です。
改定された新しい標準報酬月額は、原則として以下の期間適用されます 。
- 1月から6月までに改定された場合:その年の8月まで(その後は原則として定時決定による新しい標準報酬月額が適用されます)
- 7月から12月までに改定された場合:翌年の8月まで
この適用期間を正確に把握しておくことは、その後の給与計算や、次回の定時決定との関連を理解する上で重要です。
「定時改定(算定基礎届)」との違いと提出時期
月額変更届(随時改定)とよく比較されるのが「定時改定(算定基礎届)」です。この二つの違いを明確に理解しておくことが大切です。
- 定時改定(算定基礎届):
- 年に一度、全被保険者を対象に行われる標準報酬月額の見直しです 。
- 毎年4月、5月、6月に支払われた報酬を基に算定します。
- 算定基礎届を7月1日から7月10日までに提出します。
- 新しい標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。
- 随時改定(月額変更届):
- 固定的賃金の大幅な変動など、特定の条件を満たした場合に、その都度行われる標準報酬月額の見直しです 。
- 変動後の継続した3ヶ月間の報酬を基に算定します。
- 月額変更届を「速やかに」提出します。
- 新しい標準報酬月額は、原則として固定的賃金変動後の給与を初めて受けた月から4ヶ月目から適用されます。
重要な点として、7月、8月、または9月から随時改定が適用される従業員については、その年の定時決定(算定基礎届の提出)が不要となる場合があります 。これは、随時改定によって既に標準報酬月額が見直されるため、重ねて定時決定を行う必要がないためです。このルールを理解しておくと、不要な事務作業を減らすことができます。
月額変更届の「提出が遅れた場合」のリスクとは
月額変更届の提出が「速やかに」行われなかった場合、様々なリスクが生じる可能性があります。
遡及訂正の手間と保険料の過不足調整
提出が遅れると、本来改定されるべき月から実際に改定されるまでの期間、社会保険料が正しい金額で徴収されていない状態になります。保険料を少なく納付していた場合は、会社と従業員双方で不足分を遡って納付(または徴収)する必要が生じます。逆に多く納付していた場合は、還付や翌月以降の保険料への充当といった調整が必要となり、いずれにしても煩雑な事務処理が発生します 。
追徴金・延滞金の発生
保険料の納付不足があった場合、年金事務所の調査などで発覚すると、不足分の保険料(追徴金)に加えて、延滞金が課されることがあります 。これは企業にとって直接的な金銭的負担となります。
年金事務所からの催告・調査
提出が長期間遅れたり、提出漏れが疑われたりする場合、年金事務所から提出を促す催告状が送付されたり、場合によっては調査が行われたりすることがあります 。
法的罰則の可能性
健康保険法や厚生年金保険法では、正当な理由なく届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合の罰則が定められています。悪質なケースでは、懲役や罰金が科される可能性もゼロではありません 。
従業員との信頼関係への影響
保険料の徴収額が誤っていたり、将来の年金額に影響が出たりすることは、従業員の会社に対する不信感につながりかねません 。
遅延理由書の提出
届出が改定月の初日から60日以上遅れた場合など、大幅に遅延した場合には、月額変更届に加えて「遅延理由書」の提出を求められることがあります。また、賃金台帳や出勤簿の写しなどの添付書類も必要になる場合があります 。
これらのリスクを避けるためにも、月額変更届の提出は迅速かつ正確に行うことが極めて重要です。
月額変更届の「計算方法」を分かりやすく解説
月額変更届の提出が必要かどうかを判断し、実際に届出を行うためには、改定後の新しい標準報酬月額を正しく計算する必要があります。計算自体は平均を求めるものですが、どの期間の、どの賃金を対象とするかなど、正確な理解が求められます。
「標準報酬月額」とは何か?
まず、計算のゴールとなる「標準報酬月額」について再度確認しましょう。標準報酬月額は、健康保険料や厚生年金保険料を計算するための基準となる金額で、実際の報酬額を一定の幅で区切った等級(グレード)に当てはめて決定されます 。
健康保険の標準報酬月額は、加入している健康保険組合(協会けんぽ、組合健保など)や都道府県によって等級表が異なります。一方、厚生年金保険の標準報酬月額は全国共通の等級表が用いられます 。最新の標準報酬月額等級表は、日本年金機構のウェブサイトや、加入している健康保険組合のウェブサイトで確認できます 。特に健康保険については、自社が所在する都道府県の協会けんぽの料額表、または加入している組合健保の料額表を参照する必要がある点にご注意ください。
「固定的賃金」と「非固定的賃金」の違いを理解する
月額変更届の計算において非常に重要なのが、「固定的賃金」と「非固定的賃金」の区別です。
- 固定的賃金:
- 定義:基本給、役職手当、住宅手当、家族手当、通勤手当(定額支給の場合)など、毎月決まった額が支給される賃金や、支給単価・支給率が固定されている賃金を指します 。いわゆる「みなし残業代」として毎月定額で支払われる固定残業代も、固定的賃金に該当します 。
- 月額変更のトリガー:月額変更届(随時改定)は、この固定的賃金に変動があった場合に検討が開始されます。
- 非固定的賃金:
- 定義:残業手当、休日出勤手当、能率給(変動部分)、歩合給(変動部分)、皆勤手当など、勤務状況や業績によって毎月の支給額が変動する可能性のある賃金を指します 。
- 月額変更のトリガーにはならない:非固定的賃金のみの変動では、原則として月額変更届の対象とはなりません。
重要なポイント
月額変更届のきっかけとなるのは「固定的賃金の変動」ですが、実際に新しい標準報酬月額を計算する際の3ヶ月間の平均報酬額には、その期間に支払われた固定的賃金と非固定的賃金の両方を含めて計算します 。例えば、基本給が昇給(固定的賃金の変動)した後、その3ヶ月間に残業が多ければ、その残業手当(非固定的賃金)も平均報酬額の計算に含めます。この点が誤解されやすいため、十分にご注意ください。
以下に、固定的賃金と非固定的賃金の具体例をまとめた表を示します。
| 項目 | 固定的賃金に該当 | 非固定的賃金に該当 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 基本給 | ● | ||
| 役職手当 | ● | ||
| 住宅手当 | ● | ||
| 家族手当 | ● | ||
| 通勤手当(定額支給) | ● | ||
| 通勤手当(実費精算・変動) | ● | 毎月の実費に応じて変動する場合 | |
| 固定残業代(みなし残業代) | ● | 毎月定額で支給される部分 | |
| 通常の残業手当 | ● | 時間外労働の実績に応じて変動 | |
| 能率給・歩合給(固定単価) | ● | 単価や率が固定されている場合 | |
| 能率給・歩合給(変動実績) | ● | 実績により毎月変動する場合 | |
| 皆勤手当・精勤手当 | ● | 出勤状況により変動する場合(※毎月固定額の場合は固定的賃金となることも) | |
| 賞与(年3回以下) | 標準報酬月額の算定対象外(賞与支払届の対象) |
※上記は一般的な例であり、手当の名称だけでなく、その支給実態や就業規則・賃金規程の定めによって判断が異なる場合があります。
月額変更届の「新しい標準報酬月額」の計算ステップ
新しい標準報酬月額を計算する手順は以下の通りです。
- 固定的賃金が変動した月以降の継続する3ヶ月間を特定する
- 固定的賃金の変動が最初に給与に反映された月から数えて3ヶ月間が算定対象期間となります 。
- 各月の支払基礎日数を確認す
- 特定した3ヶ月間の各月において、支払基礎日数が17日以上(短時間労働者の場合は11日以上の場合あり)であることを確認します。1ヶ月でもこの条件を満たさない場合は、原則として月額変更の対象外となります 。
- 各月の報酬月額を計算する
- 特定した3ヶ月間の各月について、支払われた報酬の総額(固定的賃金+非固定的賃金。所得税や社会保険料を控除する前の金額)を計算します 。
- 3ヶ月間の平均報酬月額を計算する
- ステップ3で計算した3ヶ月分の報酬月額を合計し、3で割って平均額を算出します。1円未満の端数が生じた場合は切り捨てます 。
- 標準報酬月額等級表に当てはめる
- ステップ4で算出した平均報酬月額を、健康保険および厚生年金保険の標準報酬月額等級表に当てはめ、新しい標準報酬月額(と等級)を決定します 。
- 従前の標準報酬月額の等級と比較する
- ステップ5で決定した新しい標準報酬月額の等級と、従前の標準報酬月額の等級を比較し、2等級以上の差があるかを確認します。2等級以上の差があれば、月額変更届の提出が必要です。
計算例
4月に基本給が20,000円昇給し、4月、5月、6月の給与が以下のように支払われた場合(支払基礎日数はすべて17日以上とします)。
- 従前の標準報酬月額:240,000円 (健康保険19等級、厚生年金16等級)
- 4月支払給与(基本給+諸手当+残業代):265,000円
- 5月支払給与(基本給+諸手当+残業代):275,000円
- 6月支払給与(基本給+諸手当+残業代):270,000円
- 3ヶ月間の報酬合計:265,000円 + 275,000円 + 270,000円 = 810,000円
- 平均報酬月額:810,000円 ÷ 3 = 270,000円
- 標準報酬月額等級表(例:令和6年度東京都協会けんぽ・厚生年金)で270,000円に該当する等級を確認すると、
- 健康保険:280,000円(21等級)
- 厚生年金:280,000円(18等級)
- 等級比較:
- 健康保険:19等級 → 21等級(2等級差)
- 厚生年金:16等級 → 18等級(2等級差) この場合、健康保険・厚生年金ともに2等級以上の差が生じているため、月額変更届の提出が必要です。新しい標準報酬月額は健康保険・厚生年金ともに280,000円となります。
遡及支払があった場合の注意点(修正平均額)
昇給などが過去に遡って決定され、差額が一括で支払われた場合(遡及支払)、その差額が支払われた月を固定的賃金の変動があった月として扱います。ただし、その後の3ヶ月間の平均報酬月額を計算する際には、遡及差額分を含めずに計算した「修正平均額」を用いることが一般的です。これは、遡及差額を含めると一時的に報酬が非常に高くなり、実態と合わない標準報酬月額が設定されるのを避けるためです 。月額変更届の様式にも「修正平均額」を記入する欄があります。
月額変更届の「書き方」と添付書類リスト
月額変更届の計算が完了し、提出が必要となった場合、次は申請書の作成です。正確な記入が求められるため、慎重に進めましょう。
月額変更届の「必要書類」の入手方法
月額変更届の正式な様式は「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届」です。この様式は、日本年金機構のウェブサイトからPDF形式またはExcel形式でダウンロードできます 。常に最新の様式を使用するように心がけましょう。1枚の届書で複数名(通常5名まで)の手続きが可能です 。
※日本年金機構ウェブサイト:健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届
月額変更届の「申請書」の主な記入項目と書き方
月額変更届の主な記入項目と、その書き方のポイントは以下の通りです。日本年金機構が提供している記入例も参考にするとよいでしょう 。
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 事業所整理記号・事業所番号 | 年金事務所から付与されている記号・番号を記入します。 |
| 被保険者整理番号 | 被保険者ごとに付与されている番号を記入します。 |
| 被保険者氏名・生年月日 | 対象となる従業員の氏名と生年月日を正確に記入します。 |
| 改定年月 | 新しい標準報酬月額が適用される年月(固定的賃金変動後の給与が支払われた月から4ヶ月目)を記入します 。 |
| 従前の標準報酬月額 | 変更前の標準報酬月額(健康保険・厚生年金それぞれ)を千円単位で記入します。 |
| 従前改定月 | 変更前の標準報酬月額が適用された年月を記入します。 |
| 昇(降)給 | 「昇給」または「降給」のいずれかに〇をつけ、固定的賃金の変動があった給与の支払月を記入します。 |
| 遡及支払額 | 遡及的な支払いがあった場合に、その支払月と差額を記入します。 |
| 報酬支払基礎日数 | 固定的賃金変動後の継続した3ヶ月間の各月の支払基礎日数を記入します。17日(または11日)未満の月があっても、その月の支払基礎日数をそのまま記入します 。 |
| 通貨によるものの額 | 固定的賃金変動後の継続した3ヶ月間の各月に支払われた、金銭による報酬の総額(固定的賃金+非固定的賃金。残業手当等も含む)を記入します 。 |
| 現物によるものの額 | 食事や社宅など、現物で支給された報酬がある場合に、その価額を記入します。 |
| 合計(通貨の額+現物の額) | 通貨によるものと現物によるものの合計額を各月ごとに記入します。 |
| 総計 | 3ヶ月分の「合計」の総額を記入します。 |
| 平均額 | 「総計」を3で割った額(1円未満切り捨て)を記入します。 |
| 修正平均額 | 遡及支払があった場合に、遡及差額を除いて計算した平均額を記入します 。遡及支払がない場合は記入不要です。 |
| 備考 | 短時間労働者である場合や、昇給・降給の具体的な理由、その他特記事項がある場合に記入します 。 |
特に間違えやすい点 :
- 「給与支払月」は、給与計算の対象期間ではなく、実際に給与が支払われた月を記入します。
- 「通貨によるものの額」には、残業手当などの非固定的賃金も必ず含めて記入します。
- 支払基礎日数のカウント方法を誤らないようにします。
月額変更届に「必要な添付書類」一覧
月額変更届の提出に際して、原則として添付書類は不要です 。
ただし、以下のような特定のケースでは、添付書類の提出が求められることがあります。
- 標準報酬月額が5等級以上下がる場合
- 届出の提出が、標準報酬月額の改定月の初日から60日以上遅れた場合
- これらの場合、一般的に以下の書類の写しが必要となります。
- 賃金台帳
- 出勤簿
- これらの場合、一般的に以下の書類の写しが必要となります。
- 被保険者が役員で、報酬が大幅に下がる場合など:
- 取締役会の議事録など、報酬変更の事実を証明する書類の写し
- 業務の性質上、例年の繁忙期などにより固定的賃金が増加する企業が、年間報酬の平均で算定することを申し立てる場合(保険者算定の特例):
- 「年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用)」
- 「被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等(随時改定用)」などの専用様式

添付書類が必要かどうか不明な場合は、事前に管轄の年金事務所に確認することをお勧めします。
月額変更届の「提出先」と提出方法
書類の作成が完了したら、次は提出です。正しい提出先に、認められた方法で提出しましょう。
月額変更届の「提出先機関」
月額変更届の主な提出先は、事業所の所在地を管轄する日本年金機構の事務センターまたは年金事務所です 。
ただし、会社が加入している健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)以外の健康保険組合(組合管掌健康保険)である場合は、その健康保険組合にも月額変更届の提出が必要となる場合があります 。協会けんぽに加入している場合は、日本年金機構への提出のみで健康保険分も兼ねることが一般的です。自社が加入している健康保険の種類を確認し、必要に応じて両方の機関に提出してください。
月額変更届の「主な提出方法」(窓口、郵送、電子申請)
月額変更届の提出方法には、主に以下の3つがあります 。
- 窓口持参:管轄の年金事務所や健康保険組合の窓口に直接提出します。
- 郵送:管轄の年金事務所の事務センターや健康保険組合宛に郵送します。
- 電子申請:
- e-Gov(イーガブ):政府が運営する電子申請システムを利用して提出できます 。
- GビズIDや電子証明書:電子申請には、GビズIDの取得や電子証明書が必要となる場合があります 。
- CSVファイル添付方式:e-Govでは、届出内容をCSVファイルで作成し、添付して申請する方式などがあります 。
- 電子申請の義務化:資本金が1億円を超える法人など、一定の条件に該当する法人においては、一部の社会保険手続き(月額変更届も含む)の電子申請が義務化されています 。中小企業の皆様には直接該当しない場合も多いですが、行政手続きの電子化は進んでいます。
自社の状況や利便性に合わせて提出方法を選択できますが、電子申請は処理の迅速化やペーパーレス化の観点から推奨されています。
月額変更届を「提出しなかった場合」のリスク
月額変更届の提出を怠った場合、または提出が大幅に遅れた場合には、企業にとって様々な不利益が生じる可能性があります。これらのリスクを認識し、適切な対応を心がけることが重要です。
| リスクの種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 遡及訂正・保険料追徴 | 過去に遡って社会保険料の計算をやり直し、不足分があれば会社・従業員ともに追徴される。過払いがあれば還付・充当の手続きが必要となり、事務負担が増大する 。遡及期間は原則2年 。 |
| 延滞金 | 保険料の追徴が発生した場合、納付期限からの日数に応じて延滞金が加算されることがある 。 |
| 年金事務所からの督促・調査 | 提出漏れや遅延が長期間続くと、年金事務所から督促状が送付されたり、立入調査が行われたりする可能性がある 。 |
| 法的罰則 | 健康保険法や厚生年金保険法に基づき、正当な理由なく届出を怠ったり虚偽の届出をしたりした場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性がある 。 |
| 従業員の不利益・信頼失墜 | 正しい保険料が徴収されていないと、従業員の将来の年金額や傷病手当金などの給付額に影響が出る可能性がある。また、給与からの控除額の誤りは従業員の不信感を招き、信頼関係を損なう恐れがある 。 |
| 将来の年金額への影響(特に役員) | 特に役員報酬を変更した場合、月額変更届の提出漏れは老齢厚生年金の支給額に直接影響し、年金が減額されたり支給が遅れたりする可能性がある 。 |
これらのリスクは、金銭的な負担だけでなく、事務作業の増加、行政指導、そして最も大切な従業員との信頼関係の悪化にも繋がりかねません。
月額変更届の提出漏れによる「遡及訂正」の手間
月額変更届の提出を忘れていた場合、その事実に気づいた時点から過去に遡って社会保険料の訂正が必要になります。この遡及訂正は、原則として過去2年間分まで行うことができます 。
具体的には、以下のような手間が発生します。
- 対象となる従業員の過去の給与データを確認し、本来あるべき標準報酬月額を再計算する。
- 正しい標準報酬月額に基づいて、過去の各月の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)を再計算する。
- 会社負担分と従業員負担分の差額を算出し、不足分があれば追徴し、過払い分があれば還付または翌月以降の給与で調整する。
- 従業員に対して、遡及訂正の内容と給与からの追加徴収または還付について説明し、理解を得る。
- 会計処理や給与計算システムの修正を行う。
これらの作業は非常に煩雑であり、特に複数の従業員が対象となる場合や、長期間にわたって提出漏れがあった場合には、担当者の負担は計り知れません。
未提出・遅延による「追徴金・延滞金」のリスク
月額変更届の未提出や遅延により、本来納めるべき社会保険料よりも少ない額しか納付していなかった場合、年金事務所から不足分の保険料(追徴金)の納付を求められます 。この追徴金は、場合によっては高額になることもあり、企業の資金繰りに影響を与える可能性があります。
さらに、追徴金の納付が遅れた場合には、その遅延日数に応じて延滞金が加算されることもあります 。延滞金は日割りで計算されるため、対応が遅れれば遅れるほど負担が増加します。これらの金銭的ペナルティは、企業の経営にとって無視できないリスクと言えるでしょう。
算定基礎届との「違い」?
月額変更届(随時改定)と並んで、社会保険の手続きでよく耳にするのが「算定基礎届(定時決定)」です。この二つは目的や提出時期が異なるため、混同しないように正確に理解しておくことが重要です 。
| 比較項目 | 月額変更届(随時改定) | 算定基礎届(定時決定) |
|---|---|---|
| 目的 | 固定的賃金の大幅な変動があった場合に、実態に合わせて標準報酬月額を臨時に改定する | 全被保険者の標準報酬月額を年に一度定期的に見直し、決定する |
| 主なトリガー | 昇給・降給などによる固定的賃金の変動があり、かつ一定の条件(2等級差、支払基礎日数)を満たした場合 | 毎年7月1日現在の全被保険者 |
| 提出時期 | 随時改定の要件を満たし次第、速やかに | 毎年7月1日から7月10日まで |
| 対象となる給与計算期間 | 固定的賃金変動後の継続した3ヶ月間の報酬 | 原則として毎年4月、5月、6月に支払われた報酬 |
| 新標準報酬月額の適用月 | 原則として固定的賃金変動後の給与を初めて受けた月から4ヶ月目から | その年の9月から翌年8月まで |
| 提出頻度 | 該当する変動があった都度(不定期) | 原則として毎年1回 |
| 全従業員対象か | 該当する従業員のみ | 原則として7月1日現在の全被保険者(一部対象外あり) |
算定基礎届の「目的」と提出時期
算定基礎届は、正式名称を「被保険者報酬月額算定基礎届」といい、年に一度、すべての被保険者の標準報酬月額を決定し直す「定時決定」のために提出する書類です 。
- 目的:毎年4月、5月、6月に支払われた給与(報酬)を基に、その年の9月から翌年8月までの1年間に適用される標準報酬月額を決定します。これにより、実際の報酬額と標準報酬月額との間に大きな乖離が生じるのを防ぎ、社会保険料を適正に算定します。
- 提出時期:毎年7月1日から7月10日までの間に、管轄の年金事務所または事務センターに提出します。
月額変更届と算定基礎届の「使い分け」
この二つの届出の使い分けは以下の通りです。
- 月額変更届(随時改定): 年の途中で、昇給や降給などにより従業員の固定的賃金が大幅に変動し、かつ「2等級以上の差」と「支払基礎日数17日以上(3ヶ月間)」の条件をすべて満たした場合に提出します 。これは、定時決定を待たずに、実態に合わせて臨時に標準報酬月額を改定するための手続きです。
- 算定基礎届(定時決定): 毎年1回、原則として全被保険者を対象に、4月・5月・6月の報酬に基づいて標準報酬月額を定期的に見直すための手続きです 。
重要な関連性として、7月、8月、または9月から随時改定(月額変更届による改定)が適用される従業員については、その年の算定基礎届の提出が不要となる場合があります 。これは、随時改定によって既に新しい標準報酬月額が決定されるためです。該当する場合は、算定基礎届の備考欄にある「3.月額変更予定」に〇を付けて提出します(電子申請の場合は対象者を除いて作成)。
よくある質問 (FAQ)
月額変更届に関して、特にお問い合わせの多いご質問とその回答をまとめました。
Q1: 月額変更届を出し忘れた場合、いつまで遡及できますか?
A1: 原則として、過去2年間分まで遡って月額変更の手続きを行うことができます。この2年という期間は、健康保険法および厚生年金保険法に定められており、届出をすべきだった時点から起算されます。ただし、長期間の提出漏れは延滞金やその他のリスクも伴うため、気づき次第速やかに手続きを行うことが重要です 。
Q2: 月額変更届の提出漏れは年末調整に影響しますか?
A2: はい、影響する可能性があります。月額変更届が未提出だと、社会保険料の控除額が正しく計算されず、年末調整の際に所得税額に過不足が生じることがあります。遡って社会保険料を訂正した場合、年末調整の再計算や修正申告が必要になることもありますので注意が必要です 。
Q3: 固定的賃金が上がったが、残業代などの非固定的賃金が減って、結果的に3ヶ月平均の報酬総額があまり変わらない(または2等級以上の差がない)場合、月額変更は必要ですか?
A3: いいえ、原則として必要ありません。月額変更届の提出には、①固定的賃金の変動、②変動後の3ヶ月平均による標準報酬月額が従前と比較して2等級以上の差、③変動後の3ヶ月間の各月の支払基礎日数が17日以上、という3つの条件をすべて満たす必要があります。固定的賃金が変動しても、非固定的賃金を含めた結果として2等級以上の差が生じなければ、随時改定の対象とはなりません 。
Q4: 月額変更届の提出が遅れた場合、遅延理由書は必ず必要ですか?
A4: 必ずしも毎回必要というわけではありませんが、提出が大幅に遅れた場合(例えば、改定月の初日から60日以上経過した場合など)や、年金事務所から提出を求められた場合には、遅延理由書の提出が必要となることがあります。併せて、賃金台帳や出勤簿の写しなどの添付も求められることがありますので、提出遅れには十分注意し、遅れた場合は速やかに管轄の年金事務所に相談することをお勧めします 。
Q5: 役員報酬を変更した場合の月額変更届の注意点は何ですか?
A5: 役員報酬の変更も固定的賃金の変動に該当するため、他の従業員と同様に月額変更届の対象となります。特に注意すべき点としては、役員報酬の変更は株主総会や取締役会の決議が必要であり、その議事録等の写しが添付書類として求められることがある点です(特に報酬が大幅に下がる場合や提出が遅れた場合など)。また、役員自身が老齢厚生年金を受給している場合、報酬の変動は年金の支給調整に影響するため、月額変更届を適切に提出しないと年金の支給額が正しく計算されない、あるいは支給が一時的に停止するなどの不利益が生じる可能性があります 。
Q6: 短時間労働者(パート・アルバイト)の月額変更届で気をつけることは?
A6: 短時間労働者の場合、随時改定の条件の一つである「支払基礎日数」の基準が、通常の労働者と異なる場合があります。具体的には、特定適用事業所等(従業員数101人以上の企業など、一定の条件を満たす事業所)に勤務し、週の所定労働時間が20時間以上などの要件を満たす短時間労働者については、支払基礎日数が「17日以上」ではなく「11日以上」であれば、随時改定の対象となり得ます。その他の条件(固定的賃金の変動、2等級以上の差)は同様に適用されます。月額変更届の備考欄に「短時間労働者(特定適用事業所等)」と記載する必要もありますので、該当する従業員がいる場合は注意が必要です 。
まとめ
月額変更届は、従業員の適正な社会保険料負担と将来の年金給付のために不可欠な手続きです。提出漏れや誤りは企業にリスクをもたらすため、正確な理解と迅速な対応が求められます。専門家の活用も有効な選択肢です。
もし月額変更届に関するご相談がありましたら社労士事務所altruloopに相談ください。





社労士への外注で効率化-300x158.jpg)