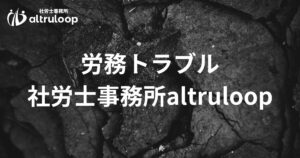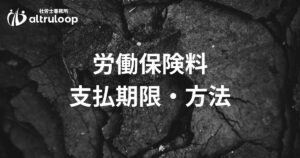「従業員の勤務態度が悪い」「能力不足で仕事が進まない」など、問題社員への対応に悩む経営者や人事担当者も多いのではないでしょうか。
しかし、安易に解雇してしまうと、不当解雇として訴えられたり、SNSで炎上したりするリスクがあります。
実際、近年は労働基準監督署への通報や労働審判の増加など、企業にとって解雇対応はますます慎重さが求められています。
そこで本記事では、解雇トラブルを防ぐための正しい相談先と、企業が必ず守るべき法律上のルールを、社労士がわかりやすく解説します。

- 即日対応
- 支援実績豊富
- 高品質なサービスを最適な価格で提供
- 解雇を行う前に確認すべきポイントが分かる
- 解雇トラブルを防ぐための事前の相談先が分かる
- 解雇トラブルで企業負うリスクが分かる
- 解雇トラブルを最小限に抑える対策が分かる
- 良くある解雇トラブルとその対策が分かる
解雇を行う前に必ず確認すべきポイント
日本は、世界でも有数の「解雇が難しい国」と言われています。
労働契約法第16条では、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効」と記されています。
つまり、勤務態度の悪さや能力不足といった理由だけでは、十分な根拠がない限り、企業側が不利になる可能性が高いのです。
そのため、解雇を検討する前には、以下の4つのポイントを確認しましょう。
- 就業規則・契約書に則った手続きか
- 注意・指導の記録が十分に残っているか
- 社内で解雇以外の手段が検討されたか
- 従業員の健康・家庭事情などを考慮しているかリスト
また、社内ルールが最新の判例や法令と整合しているかをチェックすることも重要です・トラブル発生時に、企業側の正当性を示す証拠となります。
解雇トラブルを防ぐための主な相談先
解雇トラブルを防ぐためには、社外の専門家や公的機関を活用するのが効果的です。代表的な相談先としては、以下のような選択肢があります。
| 相談先 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 社労士(社会保険労務士) | ・労働・社会保険関連の法律の専門家・懲戒処分や退職勧奨、就業規則整備などの相談に強い | ・訴訟代理は不可・紛争時は弁護士との連携が必要 |
| 弁護士 | ・紛争や訴訟対応の専門家・代理権を持ち、交渉・訴訟を担当可能 | 費用負担が大きく、予防段階にはやや不向き |
| 総合労働相談コーナー(厚生労働省) | ・労働者と事業主双方からの相談が可能・基本的なアドバイスを受けられる | 一般的な案内が中心で、個別書類の作成などは対象外 |
| なんでも労働相談ダイヤル | 無料・24時間対応(主に労働者向け) | 企業側の実務的支援や手続き相談には不向き |
企業側の実務サポートに強いのは社労士です。
社労士を中心に、必要に応じて弁護士と連携する体制を整えると、法的リスクを抑えながら対応を進められます。
解雇トラブルで企業が負う主なリスク5つ
解雇は企業の経営判断として避けられない場合もありますが、対応を誤ると法的・経済的・社会的なダメージを受けるリスクがあります。
ここでは、企業が実際に直面しやすい5つの主なリスクを解説します。
1.不当解雇の慰謝料請求
正当な理由なく従業員を解雇した場合、「不当解雇」として慰謝料を請求されるケースがあります。金額は事案によって異なり、数十万円規模の支払いが命じられるケースもあります。
たとえば、上司への批判を理由に懲戒解雇した「吉村など事件(東京地裁・平成4年)」では、解雇が不法行為と認定され、慰謝料40万円の支払いを命じられました。また、セクハラ被害を訴えた従業員を解雇した「東京セクハラ事件(東京地裁・平成11年)」でも、企業側の対応が不適切として、合計50万円の慰謝料が認められています。(※1)
一方で、企業が誠実に説明や配慮を行っていた場合は、慰謝料が認められない例もあります。つまり、解雇の手続き・説明・記録が適正であるかが重要な判断基準です。不当解雇とみなされないよう、社労士に相談して法的根拠を確認しながら進めることがリスク回避につながります。
2.バックペイ(解雇期間中の給与支払い義務)
不当解雇と判断された場合、企業は解雇から復職までの未払い給与(バックペイ)を支払う義務を負います。
裁判の確定までに1年以上かかることも多く、総額が数百万円〜1,000万円超に達するケースもあります。
また、遅延利息(年3%)や社会保険料負担も加わるため、経済的なダメージは非常に大きいでしょう。
たとえば、「解雇が無効」とされたフリービット事件(東京地裁・平成19年)では、労働者の再就職状況などを考慮して、賃金6か月分・約140万円の支払いが命じられました。(※2)
こうしたリスクを防ぐには、解雇前に改善指導や配置転換、退職勧奨などの段階的な対応を記録に残すことが重要です。
3.労働審判・訴訟の時間的・精神的コスト
解雇をめぐるトラブルは、労働審判や訴訟に発展することも珍しくありません。
労働審判は平均3回以内で終結しますが、その間に証拠提出や陳述書作成、代理人との打ち合わせが必要です。経営者や人事担当者の時間的負担は大きく、日常業務が滞ることもあります。
訴訟に進むと、解決まで半年〜2年かかることもあり、弁護士費用や対応時間の拘束、社内の士気低下など、見えないコストも発生します。
こうしたリスクを防ぐには、普段から注意指導・面談記録の整備を行い、社労士による事前のリスク診断を受けておくと安心です。
4.SNSなどでの炎上・企業イメージの悪化
近年では、解雇となった従業員がSNSで「不当な扱いを受けた」と投稿し、炎上するリスクもあります。
情報拡散は一瞬で、事実関係に関わらず、企業イメージが大きく損なわれます。特に中小企業では、ブラック企業と誤解されてしまうと、採用や取引、信用格付けなど多方面に影響が出てしまいます。こうしたリスクを防ぐには、誠実で透明性のある説明と、専門家を交えた対応が重要です。
5.従業員の士気低下・離職率上昇
解雇トラブルは、対象の従業員だけでなく、ほかの従業員にも影響を与えます。「次は自分も解雇されるのでは」といった不安が広がると、職場の信頼関係が崩れ、優秀な人材の離職につながります。このような事態を防ぐには、解雇前の信頼維持と透明性のある説明が重要です。
解雇トラブルを最小限に抑える4つの対策
解雇を適法かつ円滑に進めるためには、法律の知識だけでなく、社内ルールの整備や記録管理、従業員との適切なコミュニケーションが欠かせません。ここでは、解雇トラブルを未然に防ぐために企業が実践すべき4つの対策を解説します。
対策1.就業規則・契約書でルールを明確化する
ルールの明確化と周知は、解雇トラブルを防ぐ重要なポイントです。就業規則や雇用契約書に、懲戒事由・手続き・予告期間・解雇基準を具体的に定めておくと、企業側の判断根拠を明確にできます。
なお、解雇基準は、客観的に判断できる基準を設定することが重要です。
<例>
| 項目 | NG例(抽象的すぎる) | OK例(客観的・具体的) |
|---|---|---|
| 勤務態度 | 勤務態度が悪い | 業務命令違反や遅刻を複数回繰り返した場合 |
| 能力不足 | 能力が低い、仕事が遅い | 指導や研修を行っても、業務目標を継続的に達成できない場合 |
| 協調性 | 周囲とトラブルが多い | ほかの従業員に対し暴言・ハラスメント行為を行い、再三の注意にも改善が見られない場合 |
| 勤務不良 | やる気がない | 無断欠勤を◯日以上繰り返し、出勤指導にも応じない場合 |
また、ルールを作成しても、従業員に周知していなければ法的効力が認められないケースがあります。作って終わりではなく、定期的な見直しと正しい周知が欠かせません。そのためには、社労士に点検や改訂を依頼することをおすすめします。最新の法改正や判例に沿って就業規則をアップデートしておけば、企業を守る最も確実な仕組みになります。
対策2.指導・注意の履歴を記録として残す
解雇の有効性は、改善の機会を十分に与えたかどうかで判断されます。そのため、どれほど注意や面談を重ねても、記録がなければ指導なしと扱われるのが実務上の現実です。そのため、注意や面談内容は、改善指導書や始末書、メール、面談記録などの形で必ず残しておきましょう。社労士と連携してフォーマットをあらかじめ整備しておくと、日常業務のなかでも無理なく記録を残せる体制を作ることができます。
対策3.解雇以外の方法(配置転換・退職勧奨など)を検討する
解雇はあくまで最終手段です。その前に、従業員の状況に応じて、改善指導や教育、配置転換などの柔軟な対応を検討しましょう。実際、職務内容の変更や適性部署への異動で、業務改善につながるケースもあります。それでも改善が難しい場合は、本人の意思を尊重した退職勧奨(自主退職の提案)を検討しましょう。ただし、繰り返し呼び出す、退職を強く迫るなどの行為は「退職強要」とみなされるおそれがあります。社労士が同席すれば、第三者の視点から進め方を整えられ、法的リスクを避けつつ円満な解決が可能です。
対策4. 法律に基づいた正しい手順で解雇を進める
解雇は、理由が正当でも手続きに不備があるだけで無効と判断されることがあります。特に、労働契約法第16条や労基法の定めに基づき、企業は「合理的理由」と「相当な手続」を両立させる義務があります。
解雇を行う際は、以下の流れを必ず守りましょう。
- 解雇理由の明確化
- 事前の説明・警告(改善の機会を与える)
- 書面通知(解雇理由証明書)
- 社内決裁手続の遵守
従業員との面談時には感情的な対応を避け、「なぜ解雇に至ったのか」や「何を改善してほしかったのか」を丁寧に伝えることが大切です。
よくある「解雇トラブル」とその対策
実際の現場では、法律よりも「慣例」や「感情」で判断してしまい、思わぬトラブルに発展するケースが多く見られます。ここでは、特に中小企業で起こりやすい4つの解雇トラブルと対策方法を解説します。
1.仕事ができない従業員を解雇したら「不当解雇」と言われた
業務能力の低い従業員を「戦力にならないから」と解雇してしまうと、不当解雇と判断されるリスクがあります。能力不足を理由にする場合は、評価記録・指導履歴・改善の機会を与えた証拠がなければ、解雇の正当性は認められにくいのが現実です。そのため、日常的に業務評価表を作成し、改善指導書や面談記録を保存することが重要です。たとえば、「改善目標を設定し、3か月後に再評価した」のように、時系列で指導の経過を残すと、企業側が誠実に対応した証拠になります。
2.問題行動のある従業員をすぐに解雇してトラブルになった
遅刻や暴言、ハラスメントなどの問題行動に対して、感情的に「即時解雇」を行うと、後に解雇無効と判断されるリスクがあります。労働契約法では、懲戒解雇は「客観的に合理的で、社会的に相当」と認められる場合にのみ有効です。つまり、問題行動があっても、事前の注意・警告・改善の機会を与えなければ、正当な解雇とはみなされません。対策としては、注意喚起メールや面談記録、警告書を文書で残すことが重要です。また、懲戒解雇を検討する際は、必ず社労士に相談し、就業規則に沿った手続きを踏むことで、法的トラブルを未然に防げます。
3.病気・ケガ・育休中の従業員を解雇してしまった
病気休職中や育児休業中の従業員を、長期欠勤を理由に解雇することは原則として禁止されています。これは、労働契約法第16条および、育児・介護休業法で明確に定められています。こうした解雇を行うと、行政指導や損害賠償請求の対象となることもあり、企業にとって非常にリスクの高い対応です。まずは、復職支援や配置転換、リハビリ勤務など、従業員の状況に応じた選択肢を検討することが大切です。また、就業規則に「休職期間満了による自然退職」のルールを設けておくことで、法的トラブルを未然に防げます。社労士と協議し、休職制度や復職支援の運用ルールを実態に合わせて整備しておきましょう。
4.「試用期間だから簡単に辞めさせられる」と思っていた
試用期間中でも、解雇には合理的な理由が必要です。判例でも、試用期間の従業員を解雇する場合は、本採用後と同じように正当な理由と手続きが求められます。たとえば、試用期間中に「能力が不足している」と感じても、指導や評価の記録が残っていなければ、不当解雇と判断される可能性があります。トラブルを防ぐには、試用期間中も業務評価や面談の記録を残し、改善の機会を与えることが大切です。また、採用時に「評価基準」や「不適格と判断する条件」を契約書に明記しておくことで、後の紛争リスクを大きく減らせます。
まとめ|「事前相談」が解雇トラブルを防ぐ一番の方法
解雇は、企業にとって最も慎重な判断が求められる場面です。対応を誤ると、金銭的な損失だけでなく、信用や職場の信頼関係にも深刻な影響を及ぼすおそれがあります。
トラブルを防ぐためには、問題が起きてからではなく、解雇を検討する段階から専門家へ相談することが大切です。社労士に早めに相談すれば、法的リスクを整理し、企業にとって最適な対応策を事前に取ることができます。
東京都八王子・渋谷を拠点に全国対応している社労士事務所altruloopでは、解雇や労務トラブルに関する無料相談を実施しています。専門家のサポートを受けながら、安心・安全な労務対応を進めましょう。