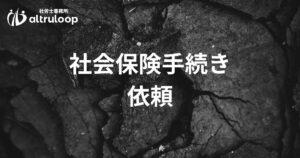社会保険制度は、私たちの生活を取り巻く様々なリスク、例えば病気、怪我、出産、死亡、老齢、障害、そして失業といった困難に直面した際に、経済的な支援や必要なサービスを提供し、生活の安定を図るための公的な保険制度です。これは、国民一人ひとりの生活を守るセーフティネットとして、また、社会全体の安定と発展を支える基盤として、極めて重要な役割を担っています 。
本記事は、複雑で多岐にわたる日本の社会保険制度について、企業経営者、人事労務担当者、そして従業員や個人事業主の皆様が、その仕組みを正しく理解し、適切に運用していくための一助となることを目的としています。社会保険制度は、頻繁な法改正や適用範囲の拡大が行われる分野でもあります。そのため、本記事では、常に最新の情報を盛り込み、実務に役立つ具体的なポイントに焦点を当てて解説を進めてまいります。
企業の担当者の方々にとっては、法令遵守はもとより、従業員の福利厚生の向上、ひいては企業価値の向上に繋がる知識を提供することを目指します。また、従業員の方々にとっては、ご自身の権利と義務を深く理解し、安心して働き、生活するための確かな基盤となる情報を提供することを目指します。本記事を通じて、社会保険制度への理解を深めていただければ幸いです。
第1章:社会保険制度の基礎知識
社会保険とは?~制度の目的と社会的役割~
社会保険とは、社会連帯の精神に基づき、病気、怪我、出産、死亡、老齢、障害、失業など、個人では対応が難しい生活上の様々なリスクに直面した場合に、相互扶助の考え方から一定の給付を行い、国民生活の安定を図ることを目的とした公的な保険制度です 。この制度は、日本国憲法第25条に定める「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を具現化するための中核的な役割を担っています。
社会保険制度の社会的役割は多岐にわたります。まず、国民皆保険・皆年金体制の根幹をなし、全国民が医療サービスを受けたり、老後の所得保障を得たりするための基盤となっています 。特に、急速な高齢化が進む現代日本において、年金制度や介護保険制度の重要性はますます高まっています 。また、医療費の補助や失業時の給付などを通じて、所得再分配機能を果たし、社会的な不平等を緩和する役割も担っています。これにより、国民全体の生活水準の向上と安定に寄与し、経済活動への積極的な参加を促すことで、社会全体の持続的な発展を支えています 。
社会保険と民間保険との主な違いは、その強制力と保障範囲にあります。社会保険は、法律で定められた要件を満たす国民および事業主に対して加入が義務付けられる強制保険であり、生活に不可欠な基本的な保障を提供することを主眼としています 。これに対し、民間保険は任意加入であり、個々のニーズに応じてより専門的または追加的な保障を得るためのものです。財源についても、社会保険は被保険者と事業主が負担する保険料および国庫負担(税金)によって賄われるのに対し、民間保険は契約者が支払う保険料によって運営されるという点で異なります。
現代社会において、社会保険制度は多くの課題にも直面しています。特に、少子高齢化の急速な進展は、年金、医療、介護といった分野での給付費の増大を招き、現役世代の保険料負担の増加という形で顕在化しています 。これは、制度の持続可能性に対する大きな挑戦であり、世代間の公平性という社会的な課題を浮き彫りにしています。「社会連帯」という社会保険の基本精神 が、この負担構造の変化の中でどのように維持され、将来にわたって機能し続けるかが問われています。今後も、保険料率の改定、給付内容の見直し、年金の受給開始年齢の引き上げ検討など、制度の持続可能性を確保するための議論は継続されるものと考えられます。企業も個人も、これらの動向を常に注視し、自らの事業計画やライフプランに適切に織り込んでいく必要があります。
企業が社会保険に加入する意義:メリットとデメリット
企業が社会保険に加入することは、単に法律で定められた義務を果たすというだけでなく、企業経営そのものに多大な影響を与える重要な要素です。社会保険への加入は、従業員の生活を支え、安心して働ける環境を提供するための基本的な福利厚生であり、企業の社会的責任の一環とも言えます。
企業が社会保険に加入するメリット
社会保険制度を適切に運用することは、企業にとって多くのメリットをもたらします。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 従業員の安心感・満足度の向上 | 健康保険や厚生年金保険への加入は、従業員にとって病気やケガの際の医療費負担の軽減、そして将来の年金受給への期待感に繋がり、大きな安心感をもたらします 。この安心感は、仕事に対する満足度を高め、結果として組織全体の士気向上に貢献します。 |
| 優秀な人材の確保と定着率の向上 | 社会保険制度の充実は、求職者にとって企業選択の重要な判断基準の一つです。福利厚生が整っている企業は魅力的に映り、優秀な人材の獲得競争において有利になります。また、既存従業員の満足度向上は、離職率の低下、すなわち人材の定着率向上にも繋がります。 |
| 生産性・モチベーションの向上 | 将来に対する経済的な不安が軽減されることで、従業員は目の前の業務により集中しやすくなります。これは、個々の従業員のモチベーション向上を促し、組織全体の生産性向上に貢献することが期待されます。 |
| 企業イメージの向上と社会的信用の獲得 | 法律を遵守し、従業員の福祉に配慮する企業としての姿勢は、社会的な評価を高めます。これは、顧客や取引先からの信頼獲得にも繋がり、良好な企業イメージの構築に貢献します 。特に近年は、企業の社会的責任(CSR)に対する関心が高まっており、社会保険の適切な運用はその基本的な取り組みとして認識されます。 |
| リスク管理 | 労災保険は業務上の事故による損害を補償し、雇用保険はリストラ時の従業員の生活を支えるなど、企業が直面しうる様々なリスクに対する備えとなります 。 |
企業が社会保険に加入するデメリット
一方で、企業が社会保険に加入することに伴う負担も存在します。
| デメリット | 詳細 |
|---|---|
| 保険料の会社負担 | 社会保険料の多くは、事業主と従業員が折半して負担します(労災保険料は全額事業主負担)。これは、企業にとって人件費の増加を意味し、特に資金体力に乏しい中小企業にとっては大きな経済的負担となる可能性があります 。従業員数が増えれば、その分負担額も増加します。 |
| 事務負担の増加 | 社会保険への加入手続き、毎月の保険料計算と納付、算定基礎届や労働保険の年度更新といった定期的な報告義務、従業員の入退社や労働条件変更に伴う諸手続きなど、煩雑な事務作業が発生します 。これらの業務には専門的な知識も必要とされ、人事労務担当者の業務負荷を増大させる要因となります。 |
企業経営において、社会保険への加入は避けて通れない課題です。デメリットとして挙げられる保険料負担や事務負担は、短期的にはコストとして認識されがちです 。しかし、メリットとして挙げられる従業員の安心感の醸成、それに伴う人材の確保・定着、生産性の向上といった効果は、長期的な視点で見れば企業価値を高める「投資」と捉えることができます。特に、労働力人口の減少が進み、人材獲得競争が激化する現代においては、福利厚生の中核である社会保険制度の充実は、企業の持続的な成長と競争力強化に不可欠な要素と言えるでしょう。経営者は、社会保険を単なる法的義務やコストとして消極的に捉えるのではなく、従業員のエンゲージメントを高め、企業価値を創造するための戦略的な投資として位置づける視点が求められます。
社会保険の主な種類と概要
日本の社会保険制度は、主に以下の5つの保険から構成されており、それぞれが異なるリスクに対応し、国民生活を多角的に支えています。
| 保険 | 詳細 |
|---|---|
| 健康保険 | 業務外の病気やケガ、または出産や死亡といった事態に備えるための医療保険制度です。加入者(被保険者)やその家族(被扶養者)は、医療機関で保険証を提示することにより、かかった医療費の一部(原則1割から3割)を自己負担するだけで、必要な医療サービスを受けることができます。 |
| 厚生年金保険 | 主に会社員や公務員などが加入する公的年金制度です。被保険者が高齢になった場合(老齢年金)、病気やケガで障害が残った場合(障害年金)、または死亡した場合(遺族年金)に、年金または一時金が支給されます 。国民年金(基礎年金)に上乗せされる形で給付が行われるため、「2階建て」の年金制度の2階部分に位置づけられています 。 |
| 介護保険 | 加齢に伴って介護が必要となるリスクに社会全体で備えるための制度です。原則として40歳以上の国民が被保険者となり保険料を負担し、要介護状態または要支援状態と認定された場合に、介護サービス(訪問介護、デイサービス、施設入所など)を利用できます。 |
| 雇用保険 | 労働者が失業した場合に、生活の安定を図りつつ再就職を支援するための給付(基本手当など)を行うほか、育児休業や介護休業を取得する労働者への給付、教育訓練を受ける労働者への支援なども行います 。 |
| 労災保険(労働者災害補償保険) | 労働者が業務上の事由または通勤の途中で負傷、疾病、障害を負ったり、死亡したりした場合(労働災害)に、被災した労働者やその遺族に対して、治療費の給付、休業中の所得補償、障害が残った場合の年金・一時金、遺族への年金・一時金などを支給する制度です。また、被災労働者の社会復帰の促進事業なども行っています。 |
これらの各保険制度は、それぞれ独立した目的と機能を持っていますが、全体として見ると、国民生活を脅かす様々なリスクに対して重層的なセーフティネットを形成しています。例えば、業務中に大きな怪我を負い、長期間働くことができなくなった場合を考えてみましょう。まず、治療にかかる費用は労災保険の「療養(補償)給付」で賄われ、休業中の所得は「休業(補償)給付」によって一定程度補償されます。もし、その怪我が原因で障害が残ってしまった場合には、労災保険から「障害(補償)給付」が支給され、さらに厚生年金保険からも「障害厚生年金」が支給される可能性があります。
このように、個々のライフイベントや直面する状況に応じて、異なる社会保険制度が発動し、連携して生活を支える仕組みになっています。そのため、企業の人事労務担当者や従業員自身が、どの保険がどのような状況で役立つのかを横断的に理解しておくことは非常に重要です。これにより、万が一の際に適切な給付を確実に受けられるようになり、また、制度の切れ目が生じないように、加入や変更、喪失といった各種手続きを正確かつ遅滞なく行うことの重要性も一層高まります。
第2章:【種類別】各社会保険制度の詳細
健康保険制度
健康保険制度は、会社の従業員やその家族(被扶養者)が、業務外の病気やケガ、あるいは出産や死亡といった事態に直面した際に、必要な医療給付や手当金を支給することで、生活の安定を図ることを目的とした医療保険制度です 。加入者は、医療機関の窓口で健康保険証を提示することにより、実際にかかった医療費の一部(年齢や所得に応じて1割~3割)を支払うだけで、診察、薬剤の支給、入院などの医療サービスを受けることができます 。
保険者
健康保険の運営主体(保険者)は、主に以下の2種類です 。
| 保険者 | 詳細 |
|---|---|
| 全国健康保険協会(協会けんぽ) | 主に中小企業の従業員が加入する健康保険です。全国規模で運営されており、保険料率は都道府県ごとに設定されています。 |
| 健康保険組合(健保組合) | 大企業が単独で設立する「単一健保組合」や、同種・同業種の複数の企業が共同で設立する「総合健保組合」があります。健康保険法に基づき設立される公法人であり、一定の従業員規模(単独の場合は常時700人以上、共同設立の場合は合計で常時3,000人以上)を満たす場合に設立が可能です 。 健康保険組合に加入する大きなメリットとして、協会けんぽと比較して保険料率が低く設定される場合があることや、法律で定められた保険給付(法定給付)に加えて、組合独自の「付加給付」が受けられる場合がある点が挙げられます。 |
企業が健康保険組合を設立・運営する、あるいは既存の組合に加入するという選択は、従業員の福利厚生の充実と企業の保険料負担の最適化を両立させる可能性を秘めています。特に、従業員の健康維持・増進への投資は、長期的に見れば欠勤率の低下や労働生産性の向上に繋がり、企業経営にもプラスの効果をもたらすと考えられます 。ただし、組合の財政状況は母体企業の業績や加入者の医療費動向に左右されるため、安定的な運営には適切なリスク管理が求められます。
被保険者・被扶養者
健康保険の加入対象者(被保険者)は、適用事業所に常時使用される従業員です。また、被保険者に生計を維持されている一定範囲の家族は、被扶養者として健康保険の給付を受けることができます 。
主な保険給付の種類
健康保険から受けられる主な給付には、以下のようなものがあります。
| 給付 | 詳細 |
|---|---|
| 療養の給付 | 病気やケガをした際に、医療機関で診察、薬剤の支給、処置、手術、入院などの医療サービスを自己負担(原則3割、未就学児2割、70歳以上75歳未満2割または3割)で受けられます。 |
| 高額療養費制度 | 1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合に、その超えた部分が払い戻される制度です。 |
| 傷病手当金 | 病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 |
| 出産育児一時金 | 被保険者またはその被扶養者が出産した際に支給されます。 |
| 出産手当金 | 被保険者が出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に支給されます。 |
保険料
健康保険料は、被保険者の標準報酬月額(毎月の給与を等級分けしたもの)と標準賞与額(税引前の賞与額から千円未満を切り捨てたもの)に、保険料率を乗じて計算されます。算出された保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担(労使折半)します。保険料率は、加入している保険者(協会けんぽの場合は都道府県ごと、健康保険組合の場合は組合ごと)によって異なります。
厚生年金保険制度
厚生年金保険制度は、主に会社員や公務員など、企業や組織に雇用されて働く人々が加入する公的年金制度です。この制度は、加入者(被保険者)が老齢になった場合、病気やケガによって障害の状態になった場合、または死亡した場合に、本人やその遺族の生活の安定を図るために、年金または一時金を支給することを目的としています 。
日本の公的年金制度は、しばしば「3階建て」と表現されます。その1階部分に当たるのが、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金(基礎年金)です。厚生年金保険は、この国民年金に上乗せされる形で給付が行われるため、2階部分に位置づけられています 。
被保険者
厚生年金保険の被保険者となるのは、適用事業所(厚生年金保険の加入が義務付けられている事業所)に常時使用される70歳未満の従業員です 。国籍や性別、年金額の多少にかかわらず、加入要件を満たせば被保険者となります。
主な保険給付の種類
厚生年金保険から支給される主な年金には、以下の3種類があります。
| 年金 | 詳細 |
|---|---|
| 老齢厚生年金 | 原則として65歳から、国民年金の老齢基礎年金に上乗せして支給されます。受給資格期間(保険料納付済期間など)を満たし、かつ厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あることが必要です。支給額は、加入期間中の平均標準報酬額や加入月数などに基づいて計算されます。 |
| 障害厚生年金 | 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある病気やケガによって、法令で定められた障害の状態になった場合に支給されます。障害の程度に応じて1級から3級までの等級があり、障害基礎年金に上乗せされる形で支給される場合や、一時金として障害手当金が支給される場合もあります。 |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が死亡した場合に、その方によって生計を維持されていた遺族(配偶者、子、父母など一定の範囲)に支給されます。 |
企業年金制度との関連
厚生年金保険は公的年金制度の2階部分ですが、企業によっては、これに加えてさらに手厚い老後の所得保障を提供するために、独自の企業年金制度(3階部分)を設けている場合があります。主な企業年金制度には、以下のようなものがあります 。
| 主な企業年金制度 | 詳細 |
|---|---|
| 厚生年金基金 | かつては多くの企業で採用されていましたが、法改正により現在は新規設立が認められておらず、既存の基金も他の制度への移行が進んでいます。国の老齢厚生年金の一部を代行し、さらに基金独自の上乗せ給付を行っていました。 |
| 確定給付企業年金(DB) | 企業が従業員に対して、将来支給する年金額をあらかじめ約束するタイプの企業年金です。運用リスクは主に企業が負います。 |
| 企業型確定拠出年金(DC) | 企業が掛金を拠出し、従業員自身がその資金を運用して、その運用成果によって将来の給付額が変動するタイプの企業年金です。運用リスクは従業員が負います。 |
これらの企業年金制度は、従業員の老後の生活設計において重要な役割を果たします。
とは?活用、法改正まで社労士が解説-300x158.jpg)
保険料
厚生年金保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に、共通の保険料率を乗じて計算されます。算出された保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担(労使折半)します。現在の厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。
日本の公的年金制度は、現役世代が納める保険料で高齢者世代の年金給付を支える「賦課方式」を基本としています。しかしながら、急速な少子高齢化の進行 は、年金制度の支え手である現役世代の減少と、受給者である高齢者世代の増加という構造的な課題を生み出しています。これにより、年金財政の厳しさが増し、制度の持続可能性が常に社会的な議論の的となっています。 このような背景から、将来にわたって年金制度を維持していくために、過去にも保険料率の段階的な引き上げや支給開始年齢の引き上げ、給付水準の調整(マクロ経済スライドの導入など)といった様々な改革が行われてきました。今後も、社会経済情勢の変化に応じて、さらなる制度の見直しが検討される可能性は否定できません。 企業や従業員にとっては、公的年金制度の動向を注視するとともに、厚生年金だけに依存するのではなく、企業年金や個人型確定拠出年金(iDeCo)、私的な貯蓄や投資など、多様な手段を組み合わせて老後の生活資金を準備していくことの重要性がますます高まっていると言えるでしょう。
介護保険制度
介護保険制度は、加齢に伴い介護が必要となるリスクに対して、社会全体で支え合うことを目的とした社会保険制度です 。急速な高齢化の進展と核家族化により、家族だけで介護を担うことが困難になっている社会的背景から、2000年4月に創設されました。
被保険者
介護保険の被保険者は、年齢によって以下の2種類に区分されます 。
- 第1号被保険者
- 65歳以上の者。 市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の方が対象です。原因を問わず、日常生活において介護や支援が必要であると市区町村から認定(要介護認定・要支援認定)を受けた場合に、介護サービスを利用できます。
- 第2号被保険者
- 40歳から64歳までの医療保険加入者。 市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満で、健康保険や国民健康保険などの公的医療保険に加入している方が対象です。第2号被保険者の場合、介護サービスを利用できるのは、加齢に伴って生じる特定の疾病(末期がん、関節リウマチ、脳血管疾患など、法令で定められた16種類の特定疾病)が原因で要介護・要支援状態になった場合に限られます。
企業の人事労務管理において主に関わるのは、従業員である第2号被保険者に関する取り扱いです。
保険料の徴収
- 第2号被保険者の保険料
- 従業員が加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)の保険料と一体的に徴収されます 。具体的には、毎月の給与や賞与から、健康保険料と合わせて介護保険料が天引きされます。
- 徴収開始時期
- 原則として、従業員が40歳に到達した月から徴収が開始されます。法律上、「40歳に到達した時」とは「40歳の誕生日の前日」を指すため、誕生日の前日が属する月から保険料が発生します。例えば、5月10日が40歳の誕生日の人の場合、5月10日の前日である5月9日に40歳に到達し、5月分の保険料から徴収対象となります。ただし、誕生日が1日の人は特例があり、例えば5月1日が誕生日の人の場合、40歳に到達するのは前月の末日(4月30日)となるため、4月分の保険料から徴収が開始されます。
- 徴収終了時期
- 従業員が65歳に到達した月の前月分まで、給与からの天引きによる徴収が行われます。65歳になると第1号被保険者に切り替わり、保険料は原則として年金からの天引き、または市区町村からの納付書により直接納付する方法に変わります )。
保険料率と負担割合
第2号被保険者の介護保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率を乗じて計算されます。算出された保険料は、健康保険料と同様に、事業主と被保険者が半分ずつ負担(労使折半)します 。 介護保険料率は、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合は全国一律で定められており、令和7年度(2025年3月分から)は1.59%です(前年度の1.60%から引き下げ)。一方、健康保険組合に加入している場合は、各組合が独自に介護保険料率を設定しています。
役員の扱い
会社の役員(社長、取締役など)であっても、40歳以上65歳未満で医療保険に加入していれば、従業員と同様に介護保険の第2号被保険者となります。したがって、役員報酬から介護保険料が計算され、徴収されます 。
介護保険制度は、高齢者が尊厳を保ちながら自立した生活を送れるよう支援するとともに、介護する家族の負担を軽減することを目的としています。しかし、現実には「介護離職」が社会問題となっています。これは、従業員が家族の介護のために仕事を辞めざるを得なくなる状況を指します。企業にとっては、貴重な人材の喪失に繋がる深刻な問題です。 この問題に対応するため、企業は介護保険制度の利用を従業員に促すだけでなく、介護休業制度の周知徹底(ただし、にあるように介護休業中の社会保険料免除はありません)、短時間勤務制度やテレワークの導入といった柔軟な働き方の選択肢を提供すること、介護に関する相談窓口を設けることなどが求められます。これらの取り組みは、従業員が仕事と介護を両立できる環境を整備し、人材の維持・確保に繋がるだけでなく、企業の社会的責任(CSR)を果たす上でも重要です。
雇用保険制度
雇用保険制度は、労働者の生活および雇用の安定と、就職の促進を目的とした社会保険制度です 。主な役割として、労働者が失業した場合に必要な給付(基本手当、いわゆる失業保険)を行い、生活の安定を図りながら再就職を支援することが挙げられます。その他にも、育児休業や介護休業を取得する労働者に対する経済的支援(育児休業給付、介護休業給付)、労働者の能力開発やキャリアアップを支援するための給付(教育訓練給付)、さらには雇用の維持・創出を図る企業への助成金(雇用調整助成金など)といった、多岐にわたる事業を行っています。
被保険者
雇用保険の被保険者となるのは、原則として適用事業所(1人でも労働者を雇用する事業所は原則として適用事業所)に雇用される労働者で、以下の2つの条件をいずれも満たす者です。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
- 31日以上の雇用の見込みがあること
正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトであっても、これらの条件を満たせば雇用保険の被保険者となります。ただし、学生(昼間学生)は原則として適用除外ですが、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務することが予定されている場合や、休学中、夜間・定時制・通信制の学生などは被保険者となる場合があります。
保険料
雇用保険の保険料は、労働者に支払われる賃金総額(基本給のほか、残業手当、通勤手当、賞与なども含む)に雇用保険料率を乗じて計算され、その保険料を事業主と労働者の双方が負担します。ただし、負担割合は均等ではなく、事業主の負担割合の方が労働者よりも若干高くなっています。
雇用保険料率は、事業の種類によって異なり、「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」の3つに区分されています 。これは、事業の種類によって失業リスクや雇用構造が異なることを反映したものです。 雇用保険料率は、失業等給付の財政状況や雇用情勢などを勘案して、毎年度見直されることになっています。例えば、新型コロナウイルス感染症の拡大局面では、雇用調整助成金の支給が急増したことなどから、雇用保険財政が逼迫し、保険料率が引き上げられた経緯があります 。
令和7年度(2025年度)の雇用保険料率については、一般の事業の場合、現行の1.55%から1.45%へと引き下げられる見込みです。内訳は、労働者負担が0.6%から0.55%へ、事業主負担が0.95%から0.9%へと、それぞれ0.05%ずつ引き下げられる案が示されています。 農林水産・清酒製造の事業については1.65%(労働者負担0.65%、事業主負担1.0%)、建設の事業については1.75%(労働者負担0.65%、事業主負担1.1%)となる見込みです 。
また、雇用保険の事業には、失業等給付のほかに、雇用安定事業(雇用調整助成金など)と能力開発事業(教育訓練給付など)があり、これらを総称して「雇用保険二事業」と呼びます。この二事業に係る保険料は、全額事業主が負担することになっており、令和7年度の料率は一般の事業で0.35%となる見込みです 。
雇用保険料率の変動は、景気や雇用情勢を敏感に反映する指標の一つと見ることができます。料率の引き上げは雇用保険財政の悪化を示唆し、逆に引き下げは財政状況の改善や雇用情勢の安定を示している可能性があります。企業にとっては、保険料率の変動が人件費コストに直接影響するため、毎年度の改定動向を注視するとともに、経済全体の動向を把握する上での一つの参考情報として活用することも考えられます。
労災保険制度
労災保険制度(正式名称:労働者災害補償保険制度)は、労働者が業務上の事由または通勤の途中で負傷、疾病にかかったり、障害が残ったり、あるいは不幸にも死亡した場合(これらを総称して「労働災害」といいます)に、被災した労働者やその遺族に対して、迅速かつ公正な保護をするために、必要な保険給付を行う制度です。また、被災労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。
適用事業所と対象労働者
労災保険は、原則として、法人・個人を問わず、一人でも労働者を使用するすべての事業所に適用されます(強制適用事業)。業種や事業規模による例外は基本的にありません。 対象となる労働者は、その事業所で使用され、賃金を支払われるすべての人です。したがって、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、契約社員、日雇い労働者など、雇用形態や呼称に関わらず、労働者であれば労災保険の保護の対象となります。
保険給付の種類
労災保険から支給される保険給付には、様々な種類があります。主なものとしては以下が挙げられます。
| 保険給付の種類 | 詳細 |
|---|---|
| 療養(補償)給付 | 労働者が業務災害または通勤災害により負傷し、または疾病にかかった場合に、必要な療養(治療)を現物給付(指定医療機関での無料診療)または現金給付(療養費の支給)として行います。 |
| 休業(補償)給付 | 療養のために働くことができず、賃金を受けられない場合に、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額(事故発生直前3ヶ月間の平均賃金)の60%相当額が支給されます。さらに、特別支給金として20%相当額が上乗せされます。 |
| 障害(補償)給付 | 傷病が治ゆ(症状固定)した後、身体に一定の障害が残った場合に、その障害の程度(第1級~第14級)に応じて、年金または一時金として支給されます。 |
| 遺族(補償)給付 | 傷病が治ゆ(症状固定)した後、身体に一定の障害が残った場合に、その障害の程度(第1級~第14級)に応じて、年金または一時金として支給されます。 |
| 葬祭料(葬祭給付) | 労働者が死亡した場合に、葬祭を行う者に支給されます。 |
| 介護(補償)給付 | 障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給しており、かつ、常時または随時介護を必要とする状態にある場合に支給されます。 |
| 二次健康診断等給付 | 職場の定期健康診断等で、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があると診断された場合に、二次健康診断および特定保健指導を無料で受けることができる制度です。 |
| 傷病(補償)年金 | 療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治ゆせず、その傷病による障害の程度が一定以上である場合に支給されます。 |
保険料
労災保険の保険料は、その全額を事業主が負担します。労働者の負担はありません。 保険料の額は、その事業所に雇用されるすべての労働者に支払われる賃金総額(毎月の給与、賞与、各種手当などを含む)に、事業の種類ごとに定められた「労災保険率」を乗じて計算されます。労災保険率は、過去の災害発生状況などを考慮して、事業の危険度に応じて細かく設定されており、例えば林業や建設業など比較的危険度の高い業種では高く、事務作業中心の業種では低く設定されています。この労災保険率は、原則として3年ごとに見直されますが、令和7年度(2025年度)の労災保険率は、令和6年度から変更がない予定です。具体的な料率は、厚生労働省が公表している「労災保険率表」で確認することができます。
未手続事業主に対する費用徴収制度
事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に労働災害が発生した場合、被災労働者には労災保険から所定の保険給付が行われますが、その事業主に対しては厳しい措置が取られます。具体的には、遡って未納分の保険料を徴収されるだけでなく、労災保険から給付された金額の全部(100%)または一部(40%)を、事業主が追加で徴収されることになります。これは、事業主が本来果たすべき加入義務を怠ったことに対するペナルティとしての意味合いを持ちます。
企業は、労働契約法等に基づき、労働者が安全で健康に働くことができるように配慮する義務(安全配慮義務)を負っています。労災保険は、万が一労働災害が発生した場合に被災労働者への補償を行う重要な制度ですが、これは企業が負う安全配慮義務を全て免除するものではありません。特に、企業の安全管理体制に不備があり、それが原因で重大な労働災害が発生した場合には、労災保険からの給付とは別に、企業が民事上の損害賠償責任を問われることもあり得ます。 したがって、企業にとっては、労災保険への加入と保険料の適正な納付を確実に行うことはもちろんのこと、それ以上に、職場の安全衛生管理体制を不断に整備・改善し、労働災害の未然防止に最大限努めることが極めて重要です。労災保険はあくまで事後的な経済的補償であり、企業の第一次的な責任は、労働災害そのものを発生させないことにあるという認識を持つべきです。
第3章:社会保険の加入条件と対象者
社会保険制度への加入は、事業所の種類や従業員の働き方によって、その義務や条件が異なります。ここでは、どのような事業所が加入義務を負い、どのような立場の人が被保険者となるのかを具体的に解説します。
加入義務のある事業所(適用事業所):法人と個人事業主の違い
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が法律で義務付けられている事業所を「適用事業所」といいます。適用事業所には、その性質により「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類があります。
強制適用事業所
以下のいずれかに該当する事業所は、事業主や従業員の意思にかかわらず、法律上当然に社会保険の適用事業所となります。
- 法人事業所:株式会社、合同会社、有限会社などの法人は、業種や従業員数、利益の有無を問わず、代表者1名のみの場合であっても原則として強制適用事業所となります。つまり、社長一人だけの会社であっても、役員報酬があれば社会保険に加入しなければなりません。
- 常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所:個人事業主であっても、常時5人以上の従業員(パート・アルバイトを含む)を使用している場合は、一部の業種(農林水産業、理容・美容業、旅館・飲食店、映画・演劇等の興行の事業など)を除き、強制適用事業所となります。
任意適用事業所
強制適用事業所に該当しない個人事業所(例えば、従業員が4人以下の個人事業所や、強制適用の対象とならない業種の個人事業所)であっても、従業員の半数以上の同意を得て、厚生労働大臣(実際の手続きは日本年金機構)の認可を受けることにより、社会保険の適用事業所となることができます。これを「任意適用事業所」といいます 。一度任意適用を受けると、原則として従業員全員が加入対象となります。
法人成りした場合の社会保険の変更点
個人事業主が事業規模の拡大などを理由に法人成り(会社を設立して事業を法人格に移行すること)した場合、社会保険の取り扱いに大きな変更が生じます。 個人事業主のときは、主に国民健康保険と国民年金に加入していましたが、法人成りすると、原則として健康保険(協会けんぽまたは健康保険組合)と厚生年金保険に加入することになります。また、従業員を雇用していれば、労災保険と雇用保険(これらを合わせて労働保険といいます)への加入も必要となります。 法人化による社会保険の変更は、保障内容の手厚さというメリットがある一方で、保険料の会社負担が発生するというデメリットも伴います。国民健康保険には被扶養者の概念がありませんが、健康保険には被扶養者制度があり、一定の条件を満たせば家族も保険給付を受けられます。また、厚生年金は国民年金に上乗せされるため、将来の年金受給額が増える可能性があります。しかし、健康保険料と厚生年金保険料は労使折半となるため、会社は従業員負担分と同額を負担する必要があり、これが経営上のコスト増に繋がります。
個人事業主が法人化を検討する際には、税務上のメリット・デメリットだけでなく、この社会保険の負担増という側面も十分に考慮し、慎重な意思決定を行う必要があります。特に、社長一人だけの会社を設立する場合でも、役員報酬を設定すれば社会保険の加入義務が生じるという点は、見落とされがちな重要なポイントです 。法人化後の役員報酬の額と、それによって変動する社会保険料の負担額を具体的にシミュレーションし、事業計画に織り込むことが不可欠です。この点については、社会保険労務士や税理士といった専門家に相談し、アドバイスを求めることが賢明でしょう。
正社員の加入条件
正社員として雇用される場合、原則として入社日から社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となることが法律で義務付けられています 。
具体的な加入条件としては、以下の点が挙げられます。
- 雇用契約の期間: 雇用期間の定めがない無期雇用契約であること、または、有期雇用契約であっても契約期間が2ヶ月を超える見込みがあること。
- 所定労働時間・日数: 1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者(いわゆる正社員)の4分の3以上であること。この「4分の3基準」が、正社員が社会保険に加入する際の基本的な目安となります。
ほとんどの正社員はこれらの条件を満たすため、入社と同時に社会保険の加入手続きが行われます。
なお、労災保険と雇用保険については、上記の健康保険・厚生年金保険の加入条件とは別に、より広い範囲の労働者が対象となります。労災保険は、原則として全ての労働者が対象となり、雇用保険は週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば加入対象となります。
ここで注意すべきは、「4分の3基準」の解釈です。この基準は、あくまで雇用契約書や就業規則で定められた「所定」の労働時間・日数を指します。しかし、契約上の時間は4分の3未満であっても、実際の勤務時間が恒常的に4分の3以上となっているような場合には、実態として加入対象者と判断され、年金事務所などから指導を受ける可能性があります。企業としては、契約上の労働時間管理だけでなく、実労働時間も適切に把握し、必要に応じて社会保険の加入状況を見直す姿勢が求められます。意図的に社会保険への加入を避ける目的で、実態と乖離した短時間契約を結ぶことは、コンプライアンス上の問題を引き起こす可能性があるため、厳に慎むべきです。
パート・アルバイト・短時間労働者の加入条件と適用拡大
パートタイマーやアルバイトといった、いわゆる短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入については、正社員とは異なる基準が設けられており、近年、その適用範囲が段階的に拡大されています。
従来の基準(4分の3基準)
まず基本的な考え方として、パート・アルバイトであっても、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者(正社員)の4分の3以上である場合は、原則として社会保険の加入対象となります 。
短時間労働者への適用拡大
上記の「4分の3基準」を満たさない短時間労働者であっても、以下の5つの要件をすべて満たす場合には、社会保険の加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること。
- 月額賃金が88,000円以上であること。 これは年収に換算すると約106万円に相当し、いわゆる「106万円の壁」として知られています。この賃金には、基本給や諸手当は含まれますが、残業代、賞与、通勤手当、臨時に支払われる手当などは含まれません。
- 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること。 当初の雇用契約期間が2ヶ月以内であっても、雇用契約書に「契約を更新する場合がある」旨の記載がある場合や、同じ事業所で同様の雇用契約により2ヶ月を超えて雇用された実績がある場合は、この要件を満たすと判断されます。
- 学生ではないこと。 ただし、卒業見込証明書を有する者で卒業前から就職し卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の者、休学中の者、大学の夜間学部や高等学校の夜間等の定時制の課程に通う者などは、適用対象となります。
- 勤務先の企業規模(厚生年金保険の被保険者数)が一定以上であること。 この企業規模要件は、段階的に拡大されています。
- 2016年10月~:従業員数501人以上の企業
- 2022年10月~:従業員数101人以上の企業
- 2024年10月~:従業員数51人以上の企業
この適用拡大により、これまで社会保険の対象外であった多くのパート・アルバイト労働者が、新たに社会保険に加入することになります。これは、より多くの労働者にセーフティネットを提供し、働き方による処遇格差を是正しようとする国の政策の表れです。
しかし、この適用拡大は、いわゆる「年収の壁」を意識するパート労働者による「働き控え」という現象を引き起こす可能性も指摘されています。社会保険に加入すると、保険料が給与から天引きされるため、手取り収入が減少することを懸念し、加入対象とならないように労働時間や収入を調整しようとする動きです。人手不足が深刻化する中で、企業にとっては労働力の確保が難しくなるという課題が生じます。 この「働き控え」問題に対応するため、企業は単に法改正への対応に留まらず、より積極的な対策を講じることが求められます。例えば、社会保険料の本人負担分の一部を補填するような手当(社会保険適用促進手当など)を導入したり、キャリアアップの機会を提供して賃金水準の向上を図ったり、正社員への転換制度を充実させたりといったインセンティブ設計が考えられます。また、社会保険加入のメリット(将来の年金額の増加、傷病手当金や出産手当金の受給資格など)を丁寧に説明し、従業員の不安を解消することも重要です。厚生労働省が設けているキャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」などを活用し、処遇改善に取り組むことも有効な手段の一つです。
役員の加入条件
会社の役員(社長、代表取締役、取締役など)の社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入については、一般の従業員とは異なる基準で判断される部分があります。
原則的な加入義務
法人の代表者や常勤の役員は、その法人から労働の対償として役員報酬を受けている場合、原則として健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。この場合、会社の従業員数や事業規模の大小は問われません。たとえ社長一人だけの会社であっても、役員報酬が支払われていれば加入義務が生じます 。
加入義務がない主なケース(例外)
ただし、以下のような場合には、役員であっても社会保険の加入義務が生じないことがあります。
- 役員報酬がない(無報酬の)場合: 法人から役員報酬を全く受けていない場合は、被保険者とはなりません 。
- 非常勤の役員である場合: 勤務実態が常勤とは言えず、例えば月に数回会議に出席するのみであったり、経営に日常的に関与していない名目的な役員であったりする場合は、加入対象外となることがあります。
- 報酬額が著しく低い場合: 役員報酬が社会保険料を納付できないほど極めて低額である場合も、加入できない(または加入しなくてもよい)とされることがあります 。
常勤・非常勤の判断基準
役員が「常勤」であるか「非常勤」であるかの判断は、単に役職名だけでなく、その勤務実態に基づいて総合的に行われます。主な判断材料としては、以下のような点が挙げられます 。
- その会社に定期的に出勤しているか。
- その会社の職務以外に、多くの他の職を兼ねていないか。
- 役員会などの重要な会議に出席しているか。
- 他の役員や従業員への連絡調整、または従業員に対する指揮監督を行っているか。
- その会社において、単に求めに応じて意見を述べる立場に留まっていないか(経営判断に実質的に関与しているか)。
- その会社から受ける報酬が、職務内容や拘束時間に見合ったものであり、単なる費用弁償的なものではないか。
これらの要素を総合的に勘案し、実質的にその法人の経営に従事していると認められる場合に常勤役員として扱われます。
雇用保険・労災保険の扱い
役員は、原則として「労働者」には該当しないため、雇用保険の被保険者とはなりません 。同様に、労災保険の保護対象からも原則として外れます。ただし、取締役でありながら部長職を兼務するなど、従業員としての身分も併せ持つ「兼務役員」で、労働者としての性格が強いと認められる場合には、雇用保険や労災保険の対象となることがあります。
従業員から役員に就任した場合の手続き
従業員が取締役に昇格するなどして役員になった場合、社会保険の取り扱いに変更が生じることがあります。 まず、雇用保険については、役員になると労働者性がなくなるため、原則として資格を喪失する手続きが必要です 。 一方、健康保険・厚生年金保険については、役員就任後も引き続き常勤で報酬を受けるのであれば、原則としてそのまま被保険者資格が継続されるため、特別な手続きは不要です 。ただし、報酬額が大幅に変動した場合は、標準報酬月額の変更手続き(月額変更届)が必要になることがあります。
役員の社会保険加入に関しては、その報酬額と社会保険料負担が密接に関連しています。特にオーナー経営者の場合、役員報酬の決定は、単に個人の所得をどうするかという問題だけでなく、会社の法人税負担や社会保険料負担を総合的に考慮した上で、会社と個人の手取り額を最適化するという視点も重要になります。例えば、役員報酬を低く抑えれば社会保険料負担は軽減されますが、個人の所得も減少し、将来の年金額にも影響します。逆に役員報酬を高く設定すれば、社会保険料負担は増えますが、個人の所得は増え、将来の年金額も増える可能性があります。 ただし、不当に低い役員報酬設定や、実態と乖離した非常勤役員の扱いは、税務署や年金事務所から否認されるリスクも伴います。したがって、役員報酬や役員の社会保険の取り扱いについては、税理士や社会保険労務士といった専門家と十分に相談し、法令を遵守した上で、個々の事情に応じた最適な判断を行うことが求められます。
特殊ケース:試用期間、複数事業所勤務
正社員やパート・アルバイト、役員といった一般的な雇用形態以外にも、社会保険の加入判断において注意が必要な特殊なケースがあります。ここでは、試用期間中の従業員と、複数の事業所で働く従業員の社会保険の取り扱いについて解説します。
試用期間中の社会保険加入
多くの企業では、本採用の前に一定期間の「試用期間」を設けています。この試用期間中の従業員であっても、社会保険の加入義務は原則として生じます。試用期間も法的には雇用契約が成立している期間であり、その期間中に社会保険の加入条件(例えば、2ヶ月を超える雇用が見込まれること、週の所定労働時間が20時間以上であることなど、前述の各加入条件)を満たしていれば、入社日から社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入させる必要があります。
ただし、例外的に加入対象外となるケースもあります。例えば、当初から雇用契約期間が2ヶ月以内と明確に定められている場合(例:2ヶ月間の短期アルバイト契約で、更新の可能性がない場合など)は、社会保険の適用が除外されることがあります 。 試用期間中であることを理由に、加入条件を満たしているにもかかわらず社会保険に加入させないことは、法律違反となる可能性があります。未加入が発覚した場合、過去に遡って加入手続き(遡及加入)を求められ、未納分の保険料に加えて追徴金や延滞金が発生するリスクがあります 。企業は、試用期間中の従業員であっても、加入条件を正しく確認し、適切に手続きを行う必要があります。
複数事業所勤務(Wワーク)の場合の社会保険
近年、副業や兼業(Wワーク)といった形で、複数の事業所で働く人が増えています。このような場合、社会保険の取り扱いは複雑になることがあります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入は、原則として主たる勤務先(最も労働時間が長い、または賃金が高いなど、総合的に判断される勤務先)で行われますが、それぞれの勤務先で社会保険の加入条件を満たすかどうかによって、対応が異なります。
両方の(または複数の)勤務先で社会保険の加入要件を満たす場合
この場合、被保険者は、自身で主たる事業所を選択し、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を管轄の年金事務所に提出する必要があります。健康保険証は選択した一方の事業所から交付されますが、保険料は各勤務先から受ける報酬月額を合算した標準報酬月額に基づいて決定され、その総保険料額を各事業所の報酬月額に応じて按分し、それぞれの事業所と被保険者が負担します。 このケースのメリットとしては、複数の勤務先からの報酬が合算されて標準報酬月額が決定されるため、将来受け取る厚生年金額が増える可能性があることや、傷病手当金などの給付額も合算後の報酬を基準に算定されるため手厚くなる可能性がある点が挙げられます。一方で、手続きが煩雑になることや、各社で保険料が控除されるため、それぞれの給与の手取り額が減少するというデメリットも考慮する必要があります 。
いずれか一方の勤務先でのみ社会保険の加入要件を満たす場合
この場合は、加入要件を満たす勤務先でのみ社会保険に加入します。もう一方の勤務先での収入は、社会保険料の算定基礎には含まれません 。
いずれの勤務先でも社会保険の加入要件を満たさない場合
この場合は、会社の社会保険には加入できず、自身で市区町村の国民健康保険および国民年金に加入する必要があります 。
働き方の多様化が進む現代において、Wワークやギグワークといった柔軟な働き方を選択する人が増えています。これに伴い、社会保険の適用関係も複雑化し、どの事業所で加入すべきか、あるいは個人で加入すべきかの判断が難しくなるケースが増えています 。 企業が従業員の副業・兼業を認める場合には、他社での勤務状況や社会保険の加入状況を適切に把握し、二重加入や未加入といった問題が発生しないよう、従業員に対して情報提供や指導を行うことが望まれます。従業員自身も、自身の働き方に応じた社会保険のルールを正しく理解し、必要な手続きを遺漏なく行うことが重要です。この領域は判断が難しい場合も多いため、企業担当者も従業員も、必要に応じて年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談することが有効な対策となります。
第4章:社会保険料の計算と負担
社会保険料は、企業と従業員の双方にとって重要な経済的負担であり、その計算方法と負担割合を正しく理解しておくことは不可欠です。ここでは、保険料計算の基礎となる考え方から、各保険料率、賞与にかかる保険料、そして保険料が免除されるケースについて解説します。
保険料計算の基礎:標準報酬月額と標準賞与額
社会保険料(主に健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)の計算は、毎月の給与や賞与の額をそのまま用いるのではなく、「標準報酬月額」と「標準賞与額」という基準額に基づいて行われます。
標準報酬月額
標準報酬月額とは、被保険者(従業員)が事業主から受ける毎月の給与などの報酬(基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当など、労働の対償として受ける全てのものを含む)を、一定の金額の幅(等級)で区分したものです。健康保険では第1級(5万8千円)から第50級(139万円)までの50等級、厚生年金保険では第1級(8万8千円)から第32級(65万円)までの32等級に分けられています。この等級ごとに定められた金額が標準報酬月額となり、これに各保険の保険料率を乗じて保険料が計算されます。
標準報酬月額の決定・改定のタイミングは主に以下の通りです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 資格取得時決定 | 従業員が入社し、新たに被保険者資格を取得した際に、その時点での報酬月額に基づいて決定されます。この標準報酬月額は、原則としてその年の8月(6月1日から12月31日までに資格取得した場合は翌年の8月)まで適用されます。 |
| 定時決定 | 毎年1回、7月1日現在の全被保険者について、その年の4月、5月、6月の3ヶ月間に受けた報酬の平均額を算出し、それに基づいて新たな標準報酬月額を決定します。この決定された標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年の8月まで適用されます。この手続きを「算定基礎届の提出」といいます。 |
| 随時改定 | 昇給や降給などにより、固定的賃金(基本給、役職手当など毎月固定的に支払われる賃金)に大幅な変動があり、その変動後の3ヶ月間に受けた報酬の平均額から算出した標準報酬月額が、従来の標準報酬月額と比較して原則として2等級以上の差が生じた場合に、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。この手続きを「月額変更届の提出」といいます。 |
| 産前産後休業・育児休業等終了時改定 | 産前産後休業や育児休業を終了し職場復帰した際に、休業前と比較して報酬が変動した場合、一定の条件を満たせば標準報酬月額を改定できます。 |
標準賞与額
標準賞与額とは、被保険者が受けた賞与(ボーナス)の額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額のことで、賞与にかかる社会保険料の計算基礎となります。ただし、年4回以上支給される賞与は、標準報酬月額の対象となる報酬とみなされます。
標準賞与額には上限が設けられています。
- 健康保険: 年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の累計額で573万円が上限です。
- 厚生年金保険: 1回の支給(同月内に複数回支給された場合は合算)につき150万円が上限です。
- 子ども・子育て拠出金: 厚生年金保険と同様に、1ヶ月あたり150万円が上限です。
標準報酬月額や標準賞与額の算定は、社会保険料の正確な徴収と、将来の年金受給額の算定基礎となるため、極めて重要です。企業の人事労務担当者は、報酬の範囲(例えば、通勤手当は含むが、出張旅費は含まないなど )を正しく理解し、算定基礎届、月額変更届、そして賞与を支払った際に提出する「被保険者賞与支払届」といった各種手続きを、法令で定められた期限内に正確に行う必要があります。これらの届出の提出漏れや遅延は、罰則の対象となる可能性もあります 。給与計算システムを導入している企業であっても、基礎となるデータ(報酬額、手当の種類など)の入力や設定が正しくなければ、誤った標準報酬月額が算定されてしまうため、定期的な確認と担当者の継続的な教育が不可欠です。
各社会保険料の保険料率と負担割合(【最新】令和7年度情報を含む)
各社会保険制度の保険料は、前述の標準報酬月額および標準賞与額に、それぞれの制度ごとに定められた保険料率を乗じて計算されます。その負担割合は、保険の種類によって異なります。以下に、令和7年度(2025年度)の最新情報を含めて解説します。
【表】令和7年度(2025年度)主要社会保険料率と負担割合一覧
| 保険種類 | 全体料率(一般の事業・協会けんぽ東京の場合) | 従業員負担率 | 会社負担率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 健康保険料 | 9.91% | 4.955% | 4.955% | 40歳未満。都道府県により異なる。2025年3月分~ |
| 介護保険料 | 1.59% | 0.795% | 0.795% | 40歳~64歳。健康保険料に上乗せ。2025年3月分~ |
| 厚生年金保険料 | 18.300% | 9.150% | 9.150% | 固定 |
| 雇用保険料 | 1.45% (見込み) | 0.55% (見込み) | 0.90% (見込み) | 事業の種類により異なる。2025年4月1日~ |
| 労災保険料 | 事業の種類による (例: 卸売業・小売業 0.3%) | 0% | 全額会社負担 | 事業の種類により0.25%~8.8%。令和7年度は変更なしの見込み |
| 子ども・子育て拠出金 | 0.36% | 0% | 全額会社負担 | 令和7年度も変更なし |
注:雇用保険料率は2024年12月時点での見込みであり、正式決定は厚生労働省の発表をご確認ください。労災保険料率は業種により大きく異なりますので、自社の業種に対応する料率をご確認ください。
この表は、企業の人事労務担当者や経営者が、来年度の社会保険料負担を迅速に把握し、予算策定や給与計算の準備を行う上で非常に価値が高いです。従業員にとっても、自身の給与から天引きされる保険料の目安を知るのに役立ちます。最新の料率を一覧化することで、個別に各省庁の情報を探し回る手間を省き、正確な情報に基づいた計画を可能にします。
健康保険料率(協会けんぽ)、介護保険料率、雇用保険料率は、社会経済情勢や各保険制度の財政状況に応じて毎年のように見直される可能性があります。厚生年金保険料率は現在18.3%で固定されていますが、将来にわたって変更がないという保証はありません。企業の人事労務担当者は、毎年発表される最新の保険料率を正確に把握し、給与計算システム等に速やかに反映させる必要があります。特に、協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なるため、自社の事業所の所在地を管轄する協会の料率を確認することが不可欠です。厚生労働省、日本年金機構、全国健康保険協会のウェブサイトなど、公的な情報源を定期的にチェックし、常に最新の情報を入手する体制を整えておくことが重要です。
賞与にかかる社会保険料
毎月の給与だけでなく、従業員に支払われる賞与(ボーナス)も、社会保険料の徴収対象となります。対象となるのは、名称の如何を問わず、労働の対償として受け取るもののうち、年3回以下の回数で支給されるものです。年4回以上支給されるものは、賞与ではなく毎月の給与(標準報酬月額の算定基礎となる報酬)として扱われます。
賞与から徴収される社会保険料は、以下の通りです。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 介護保険料(40歳以上65歳未満の被保険者の場合)
- 雇用保険料
労災保険料の算定基礎となる賃金総額にも、賞与は含まれます 。
計算方法
健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料の計算方法は、毎月の給与から徴収する場合と同様に、まず「標準賞与額」を算出し、それに各保険の保険料率を乗じて保険料額を計算します。算出された保険料額は、事業主と被保険者が半分ずつ負担(労使折半)します。 標準賞与額は、実際に支給された賞与の額から1,000円未満を切り捨てた金額です。ただし、前述の通り、健康保険と厚生年金保険(および子ども・子育て拠出金)には、それぞれ標準賞与額に上限が設けられています。
雇用保険料についても、賞与の総支給額に雇用保険料率(労働者負担分と事業主負担分をそれぞれ)を乗じて計算し、労使で分担して負担します 。
企業が賞与制度を設計・運用する際には、この社会保険料負担についても考慮に入れる必要があります。特に、業績連動型の賞与や決算賞与など、支給額や支給回数が変動する可能性のある賞与を導入・変更する場合には、それが社会保険料の計算にどのような影響を与えるのかを事前に把握しておくことが重要です。また、従業員に対して賞与を支給する際には、社会保険料が控除されることによって手取り額が変動することを明示し、誤解が生じないように丁寧な説明を心がけるべきです。
保険料の免除制度(育児休業中など)
特定の条件下では、社会保険料の支払いが免除される制度があります。代表的なものとして、育児休業期間中の免除制度が挙げられます。
育児休業期間中の社会保険料免除
子どもを養育するために育児休業を取得する被保険者については、一定の要件を満たすことで、その休業期間中の健康保険料および厚生年金保険料が、被保険者本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。これは、育児休業中の所得がない、または減少する被保険者の経済的負担を軽減し、安心して育児に専念できるようにするための措置です。
この免除制度は、令和4年10月から改正され、より柔軟な育児休業の取得に対応できるようになりました。主な改正点は以下の通りです。
| 改正点 | 詳細 |
|---|---|
| 月途中からの育児休業でも免除対象に | 従来は、原則として育児休業を開始した日の属する月から、終了した日の翌日が属する月の前月までが免除対象でした。改正後はこれに加え、育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上(休業期間中の就業予定日を除く。土日等の休日も期間に含む)の育児休業等を取得した場合も、当該月の月額保険料が免除されるようになりました。 |
| 賞与保険料の免除要件の変更 | 賞与に係る保険料については、その賞与が支払われた月の末日を含んだ連続した1ヶ月を超える育児休業等を取得している場合に限り、免除の対象となります。 |
| 連続する育児休業の取り扱い | 連続する2つ以上の育児休業等を取得する場合は、1つの育児休業等とみなして保険料免除の判断が行われます。 |
この保険料免除を受けるためには、被保険者からの申し出に基づき、事業主が管轄の年金事務所または健康保険組合に「育児休業等取得者申出書」を提出する必要があります。自動的に免除されるわけではないため、手続きを失念しないよう注意が必要です 。
介護休業期間中の社会保険料
育児休業とは異なり、家族の介護のために介護休業を取得した場合、その期間中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は免除されません。これは、介護休業の期間が育児休業と比較して一般的に短期間(原則として通算93日まで)であることなどが理由とされています。 ただし、介護休業中に会社から賃金が支払われない場合は、その期間の雇用保険料の負担は生じません 。
産前産後休業期間中の社会保険料免除
出産のために産前産後休業を取得する被保険者についても、育児休業と同様に、その休業期間中の健康保険料・厚生年金保険料が免除される制度があります(本稿で参照した資料には直接的な詳細記載は少ないものの、一般的に適用されています)。
これらの休業制度の利用を促進し、従業員が安心して休業を取得できる環境を整備することは、企業にとって人材確保や定着の観点からも重要です。そのためには、保険料免除制度の存在を従業員に周知徹底するとともに、事業主として必要な手続きを正確かつ迅速に行うことが求められます。特に、育児休業の短期間取得や分割取得など、多様なニーズに対応した免除要件は複雑な場合があるため、制度内容を正しく理解しておく必要があります。また、介護休業の場合は社会保険料の免除がないことを従業員に明確に伝え、誤解を招かないように配慮することも大切です。これらの休業中の社会保険料の取り扱いについては、就業規則等で明文化しておくことが望ましいでしょう。
第5章:社会保険の手続きガイド
社会保険制度を適切に運用するためには、事業の開始から従業員の採用、退職に至るまで、様々な場面で正確な手続きが求められます。ここでは、主要な手続きの概要と注意点を解説します。
新規事業開始時の手続き
新たに事業を開始し、法人を設立した場合や、個人事業主であっても常時5人以上の従業員を雇用するようになった場合など、社会保険の強制適用事業所に該当した際には、速やかに各種の加入手続きを行わなければなりません。
健康保険・厚生年金保険の手続き
【表】手続きと詳細
| 手続き | 詳細 |
|---|---|
| 新規適用届の提出 | 事業所が社会保険の適用を受けるために、まず「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を、適用事業所となった事実が発生した日から原則として5日以内に、管轄の年金事務所に提出します。 提出時には、法人の場合は登記簿謄本(登記事項証明書)、個人事業主の場合は事業主の住民票など、事業所の実在を証明する書類の添付が必要です 。 |
| 被保険者資格取得届の提出 | 新規適用届と同時に、または速やかに、その事業所で働く役員や従業員(加入条件を満たす者)全員分の「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出します。これも提出期限は原則として事実発生日(入社日など)から5日以内です。 |
| 被扶養者(異動)届の提出 | 被保険者に扶養している家族がいる場合は、「健康保険 被扶養者(異動)届」も併せて提出します。これにより、被扶養者も健康保険の給付を受けられるようになります。 |
労働保険(労災保険・雇用保険)の手続き
従業員を1人でも雇用した場合には、労働保険の加入手続きも必要です。
【表】手続きと詳細
| 手続き | 詳細 |
|---|---|
| 保険関係成立届の提出 | まず、事業所として労働保険の保険関係が成立したことを届け出るために、「保険関係成立届」を、従業員を初めて雇用した日の翌日から起算して10日以内に、管轄の労働基準監督署に提出します。 |
| 概算保険料申告書の提出・納付 | 次に、その年度末までに支払う見込みの賃金総額に基づいて概算の労働保険料(労災保険料と雇用保険料の合計)を計算し、「労働保険 概算保険料申告書」を作成します。これを、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に、労働基準監督署、都道府県労働局、または指定の金融機関に提出し、保険料を納付します。 |
| 雇用保険 適用事業所設置届の提出 | 雇用保険の適用事業所となったことを届け出るために、「雇用保険 適用事業所設置届」を、事業所を設置した日(従業員を初めて雇用した日など)の翌日から起算して10日以内に、管轄のハローワークに提出します。 |
| 雇用保険 被保険者資格取得届の提出 | 雇用保険の加入条件を満たす従業員について、「雇用保険 被保険者資格取得届」を、その従業員を雇用した日が属する月の翌月10日までに、管轄のハローワークに提出します。 |
【表】まとめ:新規事業開始時の主要な社会保険・労働保険手続きと期限
| 手続き書類名 | 対象保険 | 提出先 | 提出期限 | 主な添付書類・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 健康保険・厚生年金 | 年金事務所 | 事実発生から5日以内 | 法人登記簿謄本、事業主の住民票(個人の場合)など |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 健康保険・厚生年金 | 年金事務所 | 事実発生(入社日等)から5日以内 | 被扶養者がいれば被扶養者(異動)届も同時に提出 |
| 健康保険 被扶養者(異動)届 | 健康保険 | 年金事務所 | 事実発生から5日以内 | 続柄・収入を証明する書類など |
| 保険関係成立届 | 労災保険・雇用保険 | 労働基準監督署 | 従業員を初めて雇用した日の翌日から10日以内 | |
| 労働保険 概算保険料申告書 | 労災保険・雇用保険 | 労働基準監督署等 | 保険関係成立日の翌日から50日以内 | 保険料の納付も必要 |
| 雇用保険 適用事業所設置届 | 雇用保険 | ハローワーク | 事業所設置(従業員雇用)の翌日から10日以内 | 法人登記簿謄本、事業所の賃貸借契約書コピーなど |
| 雇用保険 被保険者資格取得届 | 雇用保険 | ハローワーク | 従業員を雇用した月の翌月10日まで | 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)などの確認書類 |
新規事業主や設立間もない企業の担当者にとって、多岐にわたる手続きとその期限を一覧で確認できることは、手続き漏れを防ぎ、スムーズな事業開始を支援する上で極めて重要です。各手続きの提出先も明記することで、どこに何を提出すればよいかという疑問を解消します。
特に、健康保険・厚生年金保険の新規適用届や被保険者資格取得届は、「会社設立から5日以内」や「従業員の入社日から5日以内」といった非常にタイトな期限が設定されています。これは、法人登記が完了した後、間を置かずに手続きに着手しなければ、容易に期限を超過してしまうことを意味します。そのため、会社設立の準備段階から社会保険手続きのスケジュールを具体的に把握し、必要書類を事前に準備しておくことが肝要です。手続きに不安がある場合や、本業に集中したい場合には、社会保険労務士などの専門家に設立手続きと合わせて依頼することも有効な手段と言えるでしょう。
従業員採用時の手続き(資格取得)
従業員を新たに採用した場合、その従業員が社会保険の加入条件を満たしていれば、速やかに資格取得の手続きを行わなければなりません。
健康保険・厚生年金保険の手続き
採用した従業員が健康保険・厚生年金保険の加入条件(正社員であるか、またはパート・アルバイトであっても週の所定労働時間や月額賃金などの基準を満たす場合)に該当する場合、事業主は「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を、原則として従業員が入社した日から5日以内に、管轄の年金事務所または事務センターに提出する必要があります。 この届出には、従業員の氏名、生年月日、住所、基礎年金番号またはマイナンバー、入社年月日、報酬月額などを正確に記載します。 もし、採用した従業員に扶養している家族がいる場合は、「健康保険 被扶養者(異動)届」も同時に提出し、家族を被扶養者として認定する手続きを行います。
雇用保険の手続き
採用した従業員が雇用保険の加入条件(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがあること)を満たす場合、事業主は「雇用保険 被保険者資格取得届」を、原則として従業員を雇用した日(資格取得日)の属する月の翌月10日までに、管轄のハローワークに提出しなければなりません。 この届出には、従業員の氏名、生年月日、住所、マイナンバー、資格取得年月日、雇用形態、職種、賃金などを記載します。
労災保険の手続き
労災保険については、個別の従業員を採用するたびに特別な加入手続きを行う必要はありません。事業所が労働保険の適用事業所として保険関係が成立していれば、その事業所で働くすべての労働者(パート・アルバイトを含む)は、採用された日から自動的に労災保険の保護対象となります 。
従業員を月の途中で採用した場合でも、社会保険の資格は入社日から発生し、その月の1ヶ月分の保険料が徴収されます(日割り計算はありません)。企業は、入社日を正確に把握し、遅滞なく資格取得手続きを行うことが重要です。初月の給与から保険料を控除するか、翌月の給与から控除するかは、会社の給与規定や事務処理の方法によりますが、いずれにしても資格取得日は入社日であることを従業員に明確に説明し、保険料負担に関する誤解を避けるよう努めるべきです。
従業員退職時の手続き(資格喪失)
従業員が退職した場合、事業主は社会保険の被保険者資格を喪失させるための手続きを速やかに行わなければなりません。これにより、退職後の元従業員が国民健康保険への切り替えや失業給付の受給などをスムーズに行えるようになります。
健康保険・厚生年金保険の手続き
| 手続き | 詳細 |
|---|---|
| 被保険者資格喪失届の提出 | 従業員が退職した日の翌日から原則として5日以内に、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を管轄の年金事務所または事務センターに提出します。この届出には、退職する従業員の氏名、生年月日、資格喪失年月日(退職日の翌日)、喪失原因などを記載します。 |
| 健康保険証の回収・返却 | 退職する従業員およびその被扶養者の健康保険証は、退職日までに必ず回収します。回収した健康保険証は、資格喪失届に添付するか、または別途、加入している健康保険組合や協会けんぽに返却する必要があります 。健康保険証の回収が遅れたり、退職後に不正に使用されたりすると、医療費の返還請求など、後々トラブルの原因となる可能性があるため注意が必要です。 |
| 健康保険資格喪失証明書の発行 | 退職した従業員が、国民健康保険への加入手続きや、家族の健康保険の被扶養者になるための手続きを行う際に、「健康保険資格喪失証明書」の提出を求められることがあります。この証明書は、会社が発行することもできますし、年金事務所や健康保険組合に発行を依頼することもできます。従業員から発行の申し出があった場合には、速やかに対応することが望ましいです。万が一、会社からの発行が遅れる場合や発行してもらえない場合には、退職日が確認できる「退職証明書」や「離職票」が、市区町村によっては代替書類として認められることもあります 。 |
雇用保険の手続き
| 手続き | 詳細 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者資格喪失届の提出 | 従業員が退職した日の翌日から起算して10日以内に、「雇用保険 被保険者資格喪失届」を管轄のハローワークに提出します。この届出には、退職する従業員の氏名、被保険者番号、離職年月日、離職理由などを記載します。 |
| 離職証明書の作成・提出(離職票の交付) | 退職する従業員が失業給付(基本手当)の受給を希望する場合、事業主は「雇用保険被保険者離職証明書」(通称:離職票のもとになる書類)を作成し、上記の資格喪失届と併せてハローワークに提出する必要があります 。ハローワークは、提出された離職証明書に基づいて内容を確認し、「離職票-1」および「離職票-2」を事業主に交付します。事業主は、交付された離職票を速やかに退職者本人に送付または手渡します。この離職票は、退職者が失業給付の受給手続きを行う際に必要となる重要な書類です。 |
従業員の退職に伴うこれらの社会保険手続きが遅延すると、元従業員が国民健康保険への切り替えに手間取ったり、失業給付の受給開始が遅れたりするなど、退職後の生活設計に支障をきたす可能性があります 。企業としては、従業員の退職が決定した段階で、必要な手続きと提出書類について本人に丁寧に説明し、健康保険証の確実な回収や離職票の要否確認などを計画的に進めることが求められます。円満な退職手続きと、元従業員の次のステップを妨げない迅速な対応は、企業の社会的信頼や評判管理の観点からも重要と言えるでしょう。
標準報酬月額の届出(算定基礎届・月額変更届)
健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料の計算基礎となる標準報酬月額は、一度決定された後も、定期的に、または給与額に大きな変動があった場合に、見直し(改定)の手続きが必要となります。主な手続きは「算定基礎届(定時決定)」と「月額変更届(随時改定)」です。
算定基礎届(定時決定)
毎年1回、事業主は、その年の7月1日現在の全ての被保険者(従業員)について、原則として4月・5月・6月の3ヶ月間に支払った賃金(報酬)の月平均額を算出し、これを「被保険者報酬月額算定基礎届」(通称:算定基礎届)として、7月1日から7月10日までの間に管轄の年金事務所または事務センターに届け出る必要があります。 この届出に基づいて、その年の9月から翌年8月までの1年間に適用される新たな標準報酬月額が決定されます。これを「定時決定」といいます。 ただし、6月1日以降に資格を取得した者や、6月30日以前に退職した者、7月改定の月額変更届を提出する(または提出した)者などは、算定基礎届の提出対象から除外されます 。
月額変更届(随時改定)
昇給や降給、あるいは給与体系の変更などにより、被保険者の受ける固定的賃金(基本給、役職手当など、毎月決まって支払われる賃金)に大幅な変動があった場合には、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定する必要があります。これを「随時改定」といい、そのための手続きが「被保険者報酬月額変更届」(通称:月額変更届)の提出です。
随時改定は、以下の3つの条件をすべて満たした場合に行われます。
- 固定的賃金に変動(昇給または降給)があったこと。
- 固定的賃金の変動があった月以後、継続した3ヶ月間に支払われた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比較して原則として2等級以上の差が生じたこと。
- その3ヶ月間のいずれの月も、支払基礎日数(給与計算の対象となった日数)が17日以上であること(特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合は11日以上)。
随時改定によって決定された新たな標準報酬月額は、原則として、固定的賃金の変動後、最初にその変動した報酬が支払われた月から起算して4ヶ月目の保険料から適用されます。

提出漏れ・遅延の罰則
算定基礎届や月額変更届の提出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、健康保険法や厚生年金保険法に基づき、懲役または罰金が科される可能性があります 。
実務上、特に月額変更届の提出要否の判断は誤りやすいポイントの一つです。「固定的賃金の変動」の正しい理解が重要で、例えば基本給や役職手当の変更は固定的賃金の変動に該当しますが、残業手当や能率給といった非固定的賃金の増減だけでは、原則として随時改定の対象とはなりません 。しかし、非固定的賃金であっても、その変動が固定的賃金の変動と同時期に起こり、結果として2等級以上の差が生じた場合には、随時改定の対象となることがあります。企業の人事労務担当者は、自社の給与体系における各手当の性質を正確に把握し、固定的賃金に変動があった際には、月額変更届の提出が必要かどうかを適切に判断する必要があります。判断に迷う場合には、年金事務所や社会保険労務士に確認することが推奨されます。
電子申請の活用
近年、行政手続きのデジタル化推進の一環として、社会保険・労働保険に関する多くの手続きが、インターネットを利用した電子申請に対応しています。代表的なシステムとして、政府が運営する「e-Gov(イーガブ:電子政府の総合窓口)」があります。
電子申請のメリット
社会保険手続きを電子申請で行うことには、企業にとって多くのメリットがあります。
- コスト削減:
- 時間・交通費の削減: 行政機関の窓口へ出向く必要がなくなるため、移動時間や交通費を削減できます。
- ペーパーレス化: 紙の申請書類が不要になるため、用紙代、印刷代、郵送費といったコストを削減できます。また、書類の保管スペースも不要になります。
- 業務効率の向上:
- 24時間365日申請可能: 行政機関の開庁時間に縛られることなく、いつでも都合の良い時間に申請手続きが行えます。これにより、業務の繁閑に合わせて柔軟に対応できます。
- 事務処理の迅速化: 申請データの作成や送信がオンラインで完結するため、手書きや郵送に比べて事務処理時間を大幅に短縮できます。また、申請状況をオンラインで確認できるため、進捗管理も容易になります。
- 入力ミス・記入漏れの防止: 電子申請システムには入力チェック機能が備わっている場合が多く、手書きによる記入ミスや漏れを防ぐ効果も期待できます。
- 労務管理ソフトとの連携: 多くの市販の労務管理ソフトウェアや給与計算システムは、e-GovとのAPI連携機能やCSVファイル出力機能を備えています。これにより、普段使用しているシステムから直接、または簡単な操作で電子申請用データを作成・送信でき、二重入力の手間を省き、さらなる業務効率化が図れます 。
電子申請の義務化
特定の法人においては、一部の社会保険・労働保険手続きについて電子申請が義務化されています。対象となるのは、主に以下のような法人です。
- 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社(保険業法に規定する相互会社)
- 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人)
- 特定目的会社(資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社)
これらの法人に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険の「被保険者報酬月額算定基礎届」「被保険者報酬月額変更届」「被保険者賞与支払届」や、労働保険の「年度更新に関する申告書」など、主要な手続きを電子申請で行う必要があります。
社会保険手続きの電子申請への移行は、単に個別の業務を効率化するだけでなく、企業全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する上でも重要な取り組みと位置づけることができます。特に中小企業においては、電子申請の導入を契機として、給与計算、勤怠管理、労働者名簿の管理といった他の人事労務関連業務のデジタル化も併せて進めることで、バックオフィス業務全体の生産性向上や、蓄積されたデータの分析・活用による戦略的な人事施策の立案・実行に繋がる可能性があります。導入初期には、システムの選定や操作方法の習熟にある程度の時間とコストを要するかもしれませんが、長期的な視点で見れば、そのメリットは大きいと言えるでしょう。
書類の保管義務
社会保険に関する手続きを行った際には、関連する書類を一定期間保存することが法律で義務付けられています。これらの書類は、行政機関による調査や、将来的な確認のために必要となる重要な記録です。
健康保険・厚生年金保険に関する書類
健康保険法および厚生年金保険法では、事業主に対して、健康保険および厚生年金保険に関する書類を、その完結の日(例えば、従業員の退職、解雇、死亡の日など、その書類に係る手続きが完了した日)から原則として2年間保存することを義務付けています。 具体的に保存すべき書類の例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 被保険者資格取得届・喪失届の控(または資格取得確認通知書・資格喪失確認通知書)
- 被保険者報酬月額算定基礎届・月額変更届の控(または標準報酬決定通知書・改定通知書)
- 被保険者賞与支払届の控
- 被扶養者(異動)届の控
- その他、健康保険組合や年金事務所との間でやり取りした各種通知書や届出書類の控
労働保険(労災保険・雇用保険)に関する書類
労働保険徴収法では、労働保険に関する書類(労働保険料の申告・納付に関する書類など)について、3年間の保存義務を定めています。 また、雇用保険法では、被保険者に関する書類(資格取得届・喪失届の控、離職証明書の控など)について、4年間の保存義務を定めています。
労働基準法に基づく書類
社会保険手続きの基礎となる情報(従業員の氏名、生年月日、入社年月日、賃金額、労働時間など)が記載されている労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカードなど)、雇入れ・解雇・退職に関する書類などは、労働基準法によって原則として5年間(ただし、当分の間は経過措置として3年間)の保存が義務付けられています。これらの書類は、社会保険料の算定根拠や加入資格の確認など、社会保険手続きの正当性を証明するためにも極めて重要です。
社会保険関連の書類には、従業員の氏名、住所、生年月日、基礎年金番号、マイナンバー(個人番号)といった機微な個人情報が多数含まれています。したがって、法定の保存義務を遵守することはもちろんのこと、これらの個人情報が漏洩したり、不正に利用されたりすることのないよう、個人情報保護法に基づいた適切な管理体制を構築・運用することが企業には求められます。具体的には、書類の物理的な保管場所の施錠管理、アクセス権限の設定、電子データで保存する場合のセキュリティ対策(パスワード設定、暗号化、アクセスログの記録など)を徹底する必要があります。また、保存期間が経過した書類については、個人情報が復元できないような形で、適切かつ確実に廃棄するための社内ルールを定めておくことも重要です。
第6章:社会保険の未加入・滞納のリスクと対策
社会保険への加入は法律で定められた企業の義務であり、これを怠った場合や保険料の納付を滞納した場合には、企業にとって様々なリスクが生じます。ここでは、具体的なリスクの内容と、万が一そのような状況に陥った場合の対策について解説します。
未加入・手続き漏れのリスク(遡及加入、追徴金、罰則)
社会保険の加入条件を満たしているにもかかわらず、事業所が加入手続きを行っていなかったり、従業員の資格取得手続きを失念していたりする場合、以下のような重大なリスクに直面する可能性があります。
遡及(そきゅう)加入と保険料の一括納付
年金事務所や労働局による調査、あるいは従業員からの申告などによって未加入の事実が発覚した場合、最大で過去2年間に遡って社会保険に加入させられることがあります。この際、過去2年分の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料など)を、事業主負担分だけでなく、本来従業員が負担すべきであった分も含めて、会社が一時的に全額を立て替えて一括で納付しなければならないケースがあります 。特に、既に退職してしまった元従業員分の保険料については、会社が本人から回収することが困難な場合も多く、大きな資金負担となる可能性があります。
追徴金・延滞金の発生
悪質な未加入と判断された場合や、遡及加入に伴う保険料の納付が遅れた場合には、通常の保険料に加えて、追徴金や延滞金が課されることがあります。これにより、本来支払うべき保険料よりもさらに多くの金額を納付しなければならなくなる可能性があります。
法律に基づく罰則
健康保険法や厚生年金保険法などでは、正当な理由なく社会保険の加入手続きを怠った事業主に対して、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金といった刑事罰が科される可能性があると規定されています。
従業員からの損害賠償請求リスク
社会保険に未加入であったために、従業員が本来受けられるはずだった保険給付(例えば、病気やケガをした際の傷病手当金、出産時の出産手当金、あるいは将来の年金など)を受けられなかった場合、その損害について会社が従業員やその家族から損害賠償を請求されるリスクがあります 。
社会保険の加入義務は法律で明確に定められており、経営者がその内容を「知らなかった」という言い訳は通用しません。未加入がもたらすリスクは、単なる金銭的な負担に留まらず、刑事罰の対象となる可能性や、企業の社会的信用の失墜といった深刻な事態を招きかねません。 したがって、経営者は、自社の事業所が社会保険の適用対象であるか、また、雇用している従業員が加入資格を満たしているかを正確に把握し、適切な管理体制を構築する責任があります。特に、会社を設立した際や、初めて従業員を雇用する際には、手続きに誤りがないよう、社会保険労務士などの専門家に相談し、指導を受けることが極めて重要です。
保険料滞納時の措置と事業への影響
社会保険料の納付は、適用事業所の義務です。万が一、経営状況の悪化などにより保険料を滞納してしまった場合、以下のような段階的な措置が取られ、事業経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
- 督促・催告と延滞金の発生
- 納付期限までに社会保険料が納付されない場合、まず年金事務所や労働局から督促状が送付されます。督促状で指定された期限までに納付しないと、電話や事業所への訪問による催告が行われることがあります。また、滞納した保険料には、法定の利率に基づき延滞金が加算されます。滞納期間が長引くほど、延滞金の額も膨らんでいきます 。
- 財産調査
- 督促や催告にもかかわらず滞納が解消されない場合、行政機関は滞納者の財産状況を調査する権限を持っています。調査の対象となるのは、預貯金、不動産、売掛金、自動車、有価証券など、換価可能なあらゆる財産です )。
- 財産の差押え
- 財産調査の結果、差し押さえるべき財産が確認され、かつ、それでもなお滞納保険料の納付が行われない場合、最終的には財産の差押えが実行されます。社会保険料の徴収は国税徴収法に準じて行われるため、裁判所の令状なしに、行政機関の権限で迅速に差押えを行うことが可能です )。 差し押さえられた財産は、公売などによって換価され、滞納保険料および延滞金に充当されます。
財産差押えが事業継続に与える影響
財産の差押えは、企業の事業継続に対して以下のような深刻な影響を及ぼします。
- 資金繰りの悪化・運転資金の枯渇
- 預金口座が差し押さえられれば、当面の運転資金が不足し、仕入れや経費の支払いが困難になります。
- 信用の失墜:
- 金融機関との関係悪化: 預金口座の差押えにより、金融機関に滞納の事実が知られ、新規融資はもちろん、既存の融資条件の見直しや取引停止といった事態を招く可能性があります。
- 取引先との関係悪化: 売掛金が差し押さえられた場合、その取引先に社会保険料滞納の事実が知られることになります。これにより、企業の経営状態に対する不安が広がり、取引の縮小や停止、あるいは与信取引の拒否といった事態に繋がる可能性があります。
- 事業運営の支障
- 事業に必要な不動産(事務所、工場、店舗など)や設備、機械などが差し押さえられれば、事業の運営そのものが不可能になることもあります。
社会保険料の滞納は、単に支払いが遅れているという問題ではなく、企業の資金繰りが極めて悪化しており、経営危機に瀕していることを示す重大なシグナルと見なされます。金融機関や取引先は、この状況を経営破綻の前兆と捉える可能性が高く、一度失った信用を回復することは容易ではありません。 企業経営者は、社会保険料の支払いを経営上の最優先事項の一つと位置づけ、資金繰り計画の中に確実に組み込んでおく必要があります。万が一、支払いが困難な状況に陥りそうになった場合には、問題を放置せず、できる限り早期に年金事務所や労働局に相談し、納付計画の見直しや猶予制度の利用など、誠実に対応策を協議することが、差押えという最悪の事態を回避するために不可欠です。
採用活動や助成金への影響
社会保険の未加入や滞納は、企業の財務や法務上のリスクだけでなく、人材採用や公的支援の活用といった面でも大きな不利益をもたらします。
ハローワークでの求人申し込みの不受理
社会保険の加入義務があるにもかかわらず未加入の状態である事業所は、ハローワーク(公共職業安定所)に求人の申し込みをしても、受理されないことがあります。ハローワークは、労働関係法令を遵守していない企業の求人を扱うことを原則として認めていないためです。これにより、企業は公的な求人チャネルを利用できなくなり、採用活動に大きな支障をきたす可能性があります。
各種助成金の受給資格の喪失
国や地方自治体が実施している様々な企業向け助成金(例えば、厚生労働省のキャリアアップ助成金など)の多くは、その受給要件として、社会保険や労働保険への適切な加入および保険料の滞納がないことを定めています。したがって、社会保険に未加入であったり、保険料を滞納していたりする企業は、これらの助成金を受給する資格を失う可能性が極めて高くなります。助成金は、企業の経営改善や人材育成、雇用維持などを支援する重要な制度であり、これを活用できないことは大きな機会損失となります。
企業イメージの低下と採用難
社会保険への未加入や滞納の事実は、求職者に対して「法令を遵守しない企業」「従業員の福利厚生を軽視する企業」、いわゆる「ブラック企業」といったネガティブな印象を与えかねません。現代の求職者は、給与や仕事内容だけでなく、企業のコンプライアンス意識や働きがい、福利厚生の充実度といった点も厳しく評価します。社会保険という基本的な制度すら整備されていない企業は、優秀な人材から敬遠され、採用競争において著しく不利な立場に置かれることになります 。結果として、人材不足が慢性化し、事業の成長や存続そのものが危うくなる可能性も否定できません。
求職者にとって、企業が社会保険に適切に加入しているかどうかは、その企業が従業員を大切にし、法令を遵守する信頼できる組織であるかを見極める上での基本的な判断材料となります。ハローワークでの求人不受理や助成金の不支給といった事態は、いわば公的機関から「法令遵守体制に問題あり」という評価を受けたに等しく、企業の社会的信用を大きく損なうものです。 企業が採用競争力を高め、優秀な人材を惹きつけ、そして事業を持続的に成長させていくためには、社会保険の適正な運用を経営の土台として確立することが不可欠です。法令遵守は、信頼される企業、選ばれる企業となるための第一歩であり、強固な採用ブランドを構築するための基礎と言えるでしょう。
滞納した場合の相談先と対処法
社会保険料の支払いが困難になり、滞納してしまった場合、または滞納しそうな状況に陥った場合には、問題を放置せず、速やかに適切な対応をとることが重要です。以下に、主な相談先と対処法を示します。
| 相談先 | 対処法 |
|---|---|
| 行政機関への早期相談 | まず、滞納している保険料の種類に応じて、管轄の行政機関に正直に状況を説明し、相談することが基本です。 健康保険・厚生年金保険・介護保険料: 管轄の年金事務所 労災保険・雇用保険料(労働保険料): 管轄の労働局または労働基準監督署 支払いが困難な理由や今後の見通しなどを具体的に伝え、納付計画について誠実に協議する姿勢を示すことで、行政機関側も相談に応じてくれる可能性があります。問題を隠蔽したり、督促を無視したりすることは、事態をさらに悪化させるだけです。 |
| 納付猶予・分納(分割納付)の申請 | 災害による被害、事業の休廃止、大幅な赤字など、一定のやむを得ない理由がある場合には、保険料の納付猶予(一定期間、納付を待ってもらう)や、分納(分割して納付する)が認められることがあります。これらの制度を利用するためには、所定の申請手続きが必要であり、事業の状況を証明する書類(財産収支状況書など)の提出が求められる場合があります。認められれば、当面の資金繰りの負担を軽減することができます。 |
| 専門家への相談 | 自力での解決が難しい場合や、行政機関との交渉に不安がある場合には、弁護士、税理士、社会保険労務士といった専門家に相談することも有効な手段です。これらの専門家は、財務状況の分析、資金繰り改善策の提案、法的な手続きの代理、行政機関との交渉支援など、専門的な知識と経験に基づいて具体的なアドバイスやサポートを提供してくれます。 |
| 資金調達方法の検討 | 当面の保険料支払いのための資金を確保する手段として、ファクタリング(売掛債権を専門業者に買い取ってもらい、早期に現金化する方法)などを検討することも考えられます。ファクタリングは、融資とは異なり、売掛先の信用力に基づいて審査されるため、自社の経営状況が厳しい場合でも利用できる可能性があります。ただし、手数料が発生するため、利用にあたっては慎重な検討が必要です。 |
| 事業再生・経営改善への取り組み | 社会保険料の滞納は、多くの場合、事業の収益性や資金繰りに根本的な問題を抱えていることの表れです。納付猶予や分納は一時的な対症療法に過ぎず、問題の根本解決には繋がりません。したがって、滞納に直面した企業は、単に支払いを遅らせるだけでなく、なぜ滞納に至ったのかという根本原因を徹底的に分析し、事業モデルの見直し、不採算部門の整理、コスト削減、新たな収益源の確保など、経営そのものの改善に真剣に取り組む必要があります。専門家の助けを借りて、具体的な事業再生計画を策定し、実行していくことが、企業の再建と持続的な発展のためには不可欠です。 |
| 最終手段としての法的整理(破産申請など) | あらゆる手段を尽くしても、どうしても保険料の支払いや事業の継続が困難であるという場合には、法人破産や(個人事業主の場合は)自己破産といった法的な整理手続きを検討することも、やむを得ない選択肢の一つとなります。これにより、法人格が消滅すれば、原則として滞納していた社会保険料の支払い義務も免除されることになります(ただし、個人の自己破産の場合、社会保険料などの租税債権は免責の対象外となる点に注意が必要です)。ただし、これは事業の終焉を意味するため、極めて慎重な判断が求められます。 |
おわりに
本記事では、日本の社会保険制度について、その基礎知識から各種制度の詳細、加入条件、保険料の計算と負担、手続き、そして未加入や滞納のリスクに至るまで、網羅的に解説してまいりました。
社会保険制度は、企業経営においても、また従業員一人ひとりの生活においても、極めて重要な役割を担っています。企業にとっては、法令を遵守し、従業員が安心して働ける環境を提供するための根幹であり、従業員にとっては、病気、老齢、失業といった様々なライフリスクに備えるためのセーフティネットです。この制度を正しく理解し、適切に運用することは、企業の持続的な発展と、従業員の福祉向上に不可欠と言えるでしょう。
しかしながら、社会保険制度は非常に複雑であり、関連法令も頻繁に改正されます。特に、適用範囲の拡大や保険料率の変更などは、企業の実務に直接的な影響を与えます。そのため、常に最新の情報を入手し、社内の管理体制を適切に整備しておくことが求められます。
社労士事務所altruloop(アルトゥルループ)では、全国対応・初回相談無料でご相談を承っております。人事労務に関するお悩みはお問い合わせよりお気軽にご相談ください。