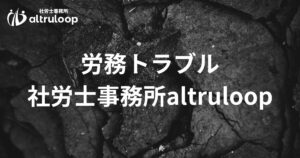今の顧問社労士に不満を抱きつつも、手間やトラブルを心配して、変更に踏み切れない経営者も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、企業が社労士を変更するよくある理由と、スムーズに引き継ぐ具体的な手順を現役社労士が解説します。今の不安を解消し、自社に本当に合う社労士と出会うためのポイントを押さえましょう。

- 手続きから給与計算まで幅広くサポート
- 社員数に合わせて柔軟な価格設定
- 助成金・補助金の提案まで実施
- 企業が社労士を変更する理由が分かる
- 企業が社労士を変えるタイミングが分かる
- 社労士を変更する際の流れが分かる
- 社労士を選ぶ際のポイントが分かる
企業が社労士を変更したくなる主な理由7つ
多くの経営者が以下のような理由から、社労士の見直しを検討しています。
- 連絡が遅い・対応が曖昧などのコミュニケーション不足
- 提案がない・知識が古いなど、専門性への不信感
- サービス内容と顧問料が見合っていない
- クラウド・電子申請など、IT対応に遅れがある
- 担当者との相性が悪く、信頼関係が築けない
- 自社の成長スピードに社労士のサポートが追いつかない
- 経営・人事の視点が欠け、単なる手続き代行に留まっている
上記のような問題が長期化している場合は、経営リスクにもつながります。
特に、法改正対応の遅れや助成金活用の機会損失は、企業の成長を妨げる要因になりかねません。また信頼できる社労士へ切り替えることで、労務リスクの軽減と業務効率化の両立が可能になります。
今の社労士に不満を感じたときの具体的な対処法については、以下の記事をご覧ください。

社労士を変えるベストなタイミング
社労士の変更は、業務の区切りや契約更新時期に合わせて行うのが理想です。
ここでは、スムーズに切り替えるためのおすすめのタイミングを紹介します。
契約更新や事業年度の切り替え時期
社労士を変更するなら、契約更新の時期が最もスムーズです。
多くの社労士事務所では、解約の申し出を1〜3か月前までに行う必要があります。この期間に合わせて新しい社労士を選べば、契約が切れるタイミングで自然に切り替えられます。
また、事業年度の始まりに合わせて変更するのもおすすめです。新しい社労士とともに、就業規則や評価制度などを見直せば、年度初めから整った労務体制を築けます。
助成金の申請を検討している場合
助成金の申請を検討している場合は、社労士を見直す良いタイミングです。最近では助成金申請を行わない先生も増えてきています。
また助成金は支給要件や準備する書類が複雑で、実績の多い事務所でないと不支給のリスクが高まります。
そのため助成金の申請を検討している場合は、そのタイミングで助成金申請を受け付けており、実績の多い事務所に切り替えるのは良いタイミングです。
組織が急拡大している場合
組織が急拡大しており、従業員数も増えている場合は、従業員規模に応じて最適な社労士事務所を選ぶのをおすすめします。
特に従業員数が100名を超えそうなタイミングやIPOの準備を始める際には、特におすすめです。
事務所によっては、従業員100人以上の企業への対応ができない場合もあるため、注意が必要です。
 野澤惇
野澤惇社労士事務所altruloop(アルトゥルループ)ではIPO準備の実績のある社労士が在籍しています!
社労士変更の具体的な手順【5ステップ】


社労士を変更するときは、感情的に動くのではなく、契約確認から引き継ぎまでを順序立てて進めることが大切です。
ここでは、社労士変更の具体的な手順を紹介します。
ステップ1.現在の契約内容と解約条件を確認する
まずは契約書を見直し、解約の通知期限や契約期間、違約金の有無を確認しましょう。併せて、顧問料の支払方法や未対応業務の精算条件の確認も重要です。契約内容を把握せずに解約すると、思わぬ追加費用や業務の中断につながることがあります。
ステップ2.変更理由と新しい社労士への依頼内容を整理する
次に、社労士を「なぜ変えたいのか」や「次に何を求めるのか」を明確にします。対応の遅さや提案の少なさ、料金体系の不透明さなど、現状の不満点を具体化しましょう。そのうえで、「今後はどんなサポートを受けたいか」を考えます。経営課題を理解してくれる社労士なのか、助成金や人事制度に強いのかなど、求める姿を整理することで、自社に本当に合うパートナー像が見えてきます。
ステップ3.複数社を比較し、最適な社労士を選ぶ
社労士を変更する際は、最低でも2〜3社の比較検討を行いましょう。
料金だけでなく、対応スピードや実績、専門分野、担当者の人柄など、複数の観点から判断することが大切です。特に、初回無料相談で課題を伝え、どんな提案をしてくれるかを比較すると、実力や相性が見えてきます。焦らず慎重に選ぶことで、後悔のない切り替えが可能になります。
ステップ4.現在の社労士に正式に解約を伝える
新しい社労士が決まったら、現社労士への解約を正式に通知します。トラブルを防ぐためにも、口頭ではなく、書面またはメールで行うのが原則です。
通知文は、形式ばった内容でなくても構いません。「契約条件に基づき、◯月末をもって契約を終了いたします」と伝えるだけで十分です。
また、通知日や解約日、精算条件などは文面に記録し、控えを保存しておきましょう。書面で残すことで、「言った・言わない」のトラブルを防げます。感情的にならず、誠実に対応することで円満な関係のまま引き継ぎを進められます。
ステップ5.新しい社労士と契約・引き継ぎを行う
新しい社労士が決まったら、まず契約内容を確認し、引き継ぎの準備を進めましょう。
主な引き継ぎ資料は、以下の通りです。
- 労働保険・社会保険の届出控え
- 就業規則
- 従業員台帳
- 給与データ
- 助成金関連書類 など
これらを整理して渡すことで、新しい社労士がスムーズに業務を引き継げます。また、1〜2か月ほどの移行期間を設け、旧社労士と新社労士の業務が重なる期間を作るのが理想です。「誰が・いつまでに・どの資料を共有するか」を明確にし、丁寧に進めることで、手続き漏れや業務中断のリスクを最小限に抑えられます。



情報をなかなか引き継がない先生がたまにいるため、余裕を持って移行期間を設けることがとても大事です。
もう失敗しない!自社に合う社労士を選ぶポイント
社労士選びで失敗しないためには、「何を重視するか」を明確にすることが大切です。料金の安さだけで判断すると、あとから対応品質に不満を感じるケースも少なくありません。
以下の5つの観点を意識することで、自社に合う社労士を見極めやすくなります。
- 専門分野・実績・得意業界が自社のニーズと合致しているか
- 相性・コミュニケーションの取りやすさ
- 提案力が高く、先回り対応ができるか
- 料金体系が明確で、納得できる価格設定か
- IT化・クラウド対応を積極的に行っているか
顧問社労士の選び方のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。


社労士事務所altruloopが選ばれる理由・強み
社労士事務所altruloop(アルトゥルループ)は、法令遵守や手続き代行だけにとどまらず、現場で実際に機能する仕組みづくりにこだわっています。経営と現場をつなぐ循環する仕組みをつくることで、企業の成長を長期的に支える。それが、私たちが提供する本質的な労務支援です。
理由1.経営戦略に寄り添う実践的な労務サポート
労務管理は単なる事務手続きではなく、経営を支える戦略の一部です。社労士事務所altruloopでは、法改正や業界の動きを踏まえ、企業の課題に合った労務体制を構築します。経営者が抱える人事・労務リスクを最小限に抑え、組織の持続的成長を支える実践的サポートを提供しています。
理由2.効率化と安心を両立するクラウド×DX支援
社会保険や給与計算など、労務業務は複雑でミスが起きやすい領域です。社労士事務所altruloopでは、クラウドツールやDXを活用し、手続きの自動化と情報共有の効率化を進めています。ペーパーレス化や電子申請にも対応し、「人に依存しない仕組み」で業務を安定化。これにより、担当者の負担を減らしながら経営者が安心して本業に集中できる環境を整えます。
理由3.顧問契約なしでも相談OK
「顧問契約を結ばないと相談できない」という従来の枠を超え、スポット相談や単発依頼にも柔軟に対応しています。初回無料相談では、現状の課題整理から改善策の方向性まで丁寧にアドバイス。経営者・人事担当者の最初の相談相手として、気軽に話せる安心感を大切にしています。
理由4.IPO・M&Aに対応できる専門性と実績
上場準備やM&Aの場面では、労務デューデリジェンス(労務監査)の精度が重要です。社労士事務所altruloopは、IPO・M&A支援に精通した社労士チームとして、上場基準に沿った労務整備や統合後の人事体制構築をサポートします。事前にリスクを洗い出し、統合後の混乱を防ぐことで、企業価値を高めながらスムーズな成長を実現します。
社労士変更に関するよくある質問(FAQ)
社労士を変更したいと考えても、「手続きは面倒?」「トラブルは起きない?」と不安に感じる方は多いでしょう。ここでは、実際のご相談で多い質問に、現役社労士がわかりやすくお答えします。
変更手続きにどれくらい時間がかかりますか?
一般的には、解約通知から引き継ぎ完了まで1〜3か月程度が目安です。契約書に記載された「解約通知期限」を確認し、スケジュールを逆算して進めましょう。
現在の社労士に引き止められたらどうすればいい?
まずは、変更理由を明確にしておくことが大切です。「新しい体制で進めたい」や「経営方針に合ったサポートを受けたい」など、前向きな理由を伝えると角が立ちません。契約上は、定められた手続きを踏めば問題なく解約できます。
変更のタイミングで労務トラブルが起きないか心配です…
適切に引き継ぎを行えば、トラブルの心配はほとんどありません。就業規則・届出控え・従業員名簿などの資料を整理して早めに共有することが重要です。届出や各種手続きは、新しい社労士が代行するため安心です。旧社労士との業務期間を1〜2か月ほど重ねておけば、手続き漏れや混乱も防げます。
まとめ|社労士変更は企業のための前向きな決断
社労士の変更は、企業の成長ステージに合わせて体制をアップデートする前向きな決断です。手順を踏んで準備すれば、手続きトラブルを避けながらスムーズに切り替えられます。
社労士を選ぶ際は、「どんな支援があれば会社がもっと良くなるか」を明確にすることが重要です。単なる手続き代行ではなく、経営をともに支えるパートナーとしての社労士を見つけられます。
社労士事務所altruloopは、企業の課題に寄り添い、現場で機能する労務の仕組みづくりを通じて、組織の成長を支えています。「今の体制を見直したい」「信頼できる社労士と出会いたい」と感じたら、まずはお気軽にご相談ください。